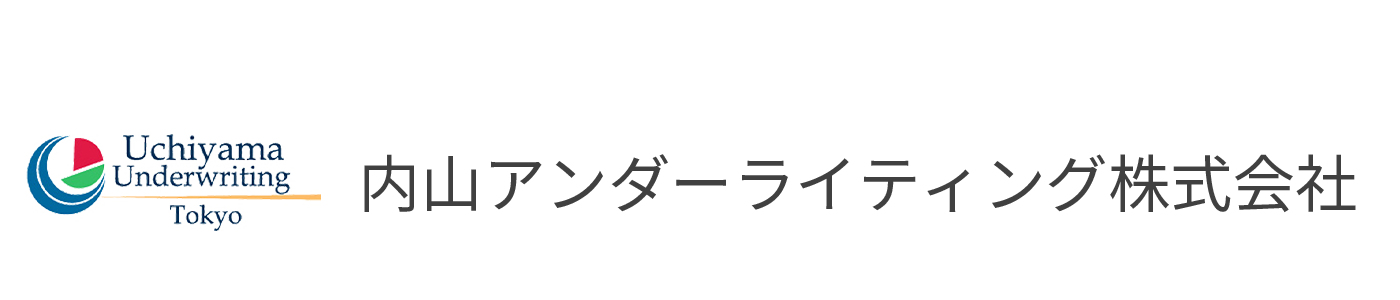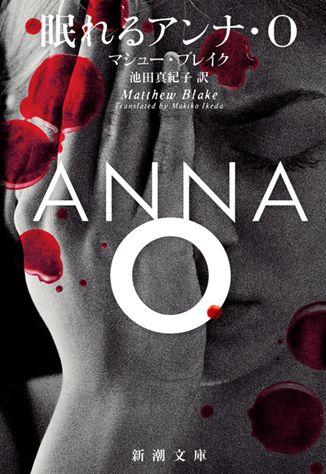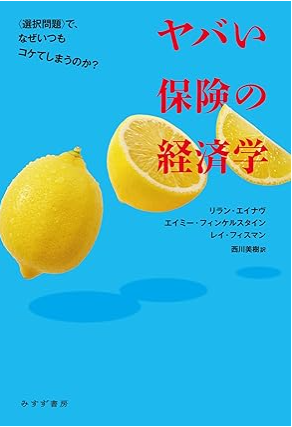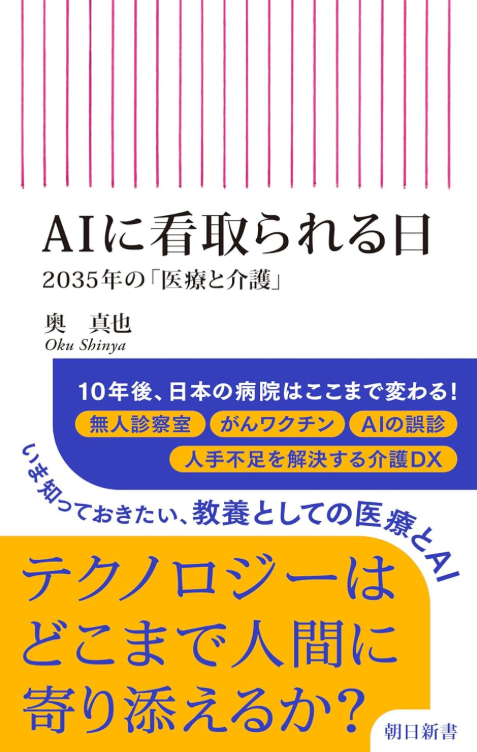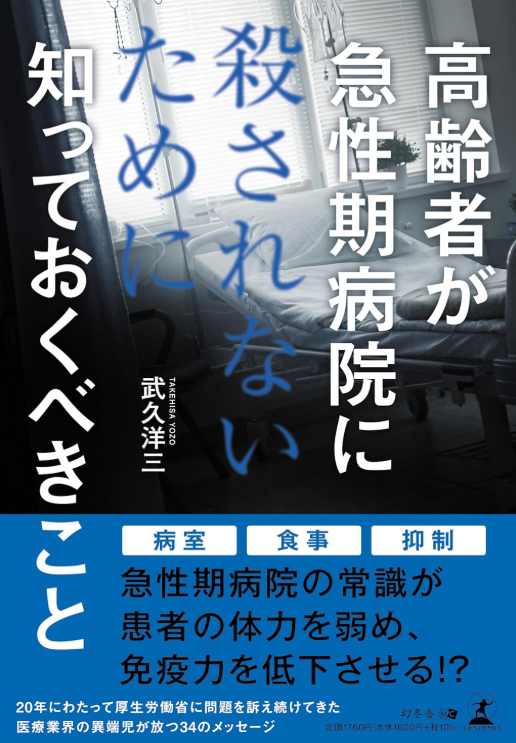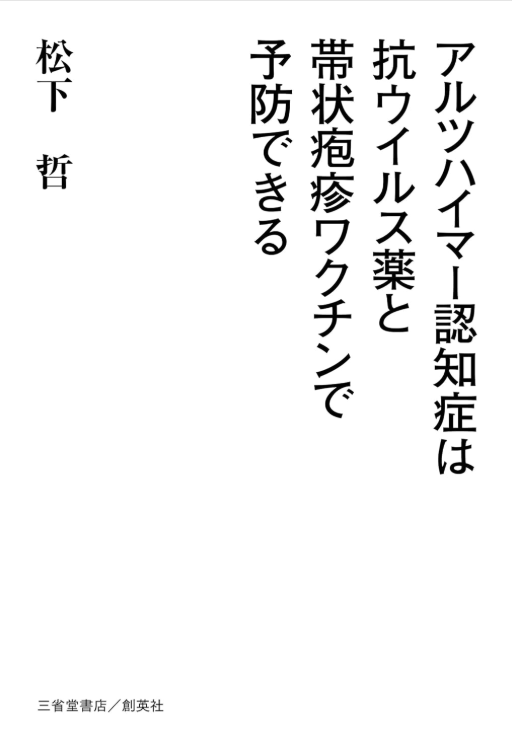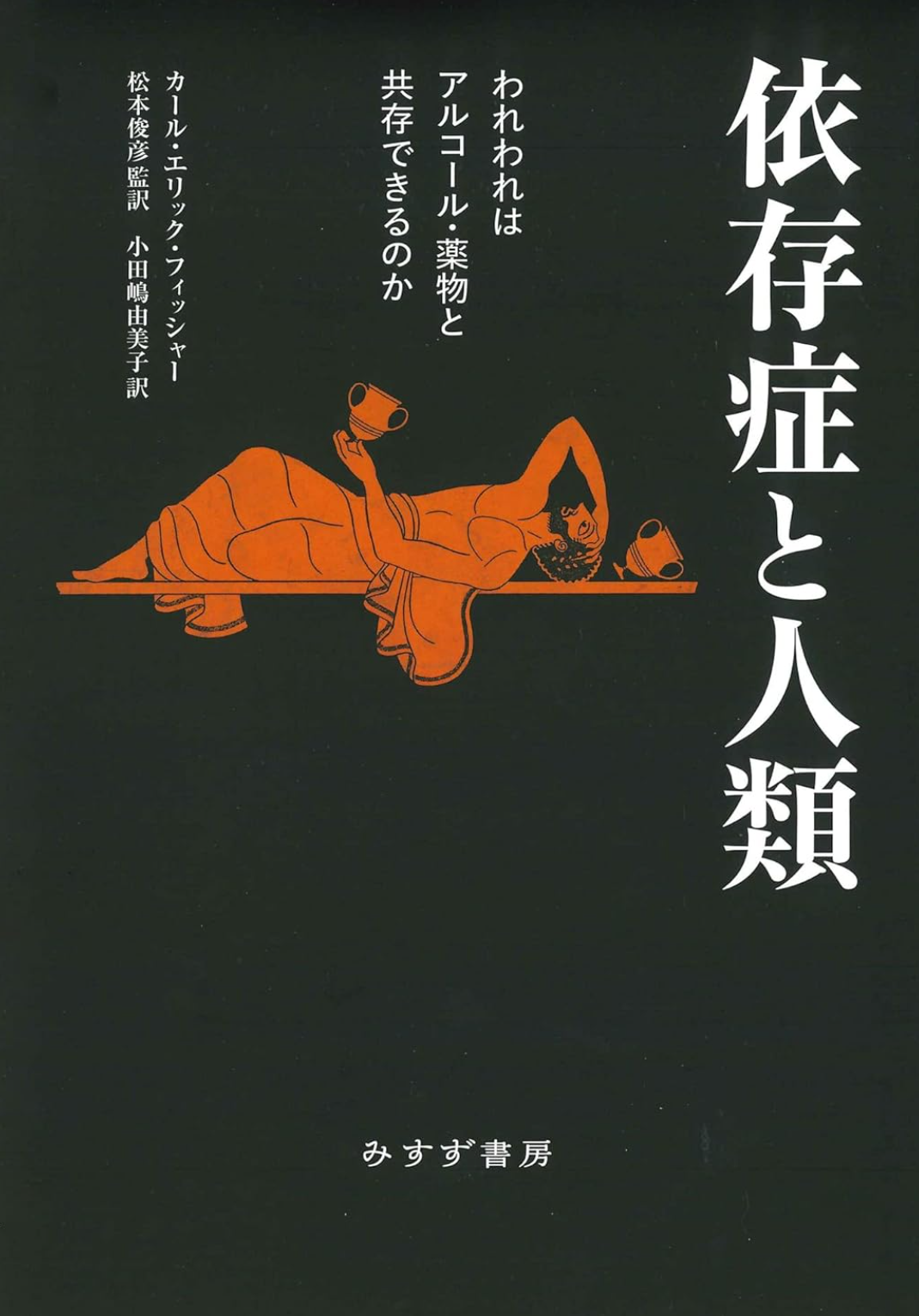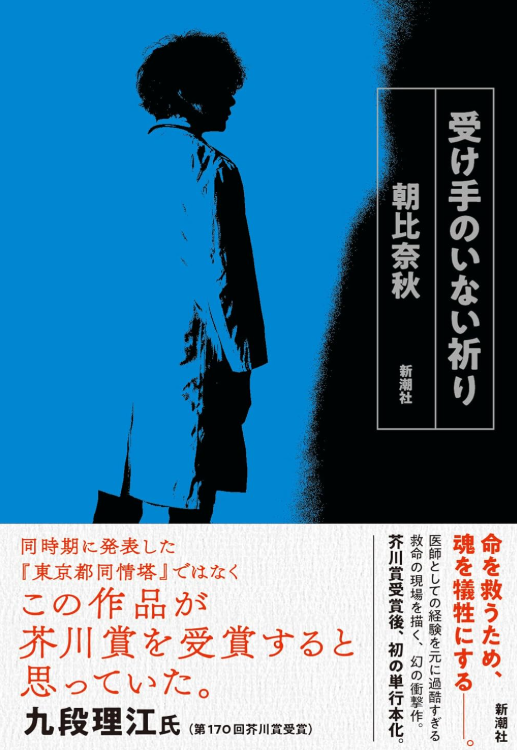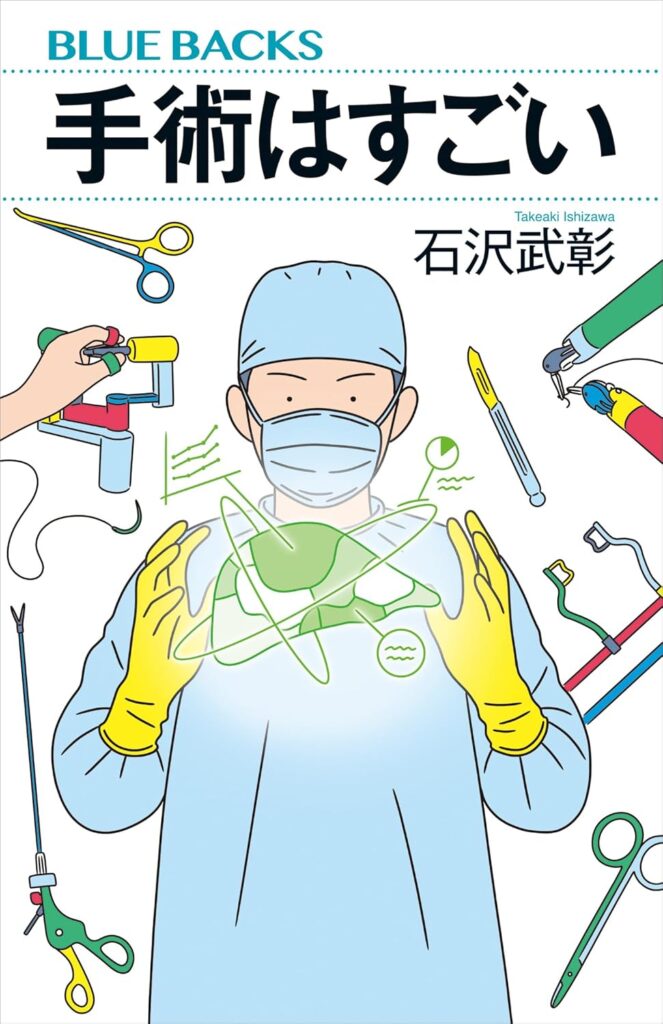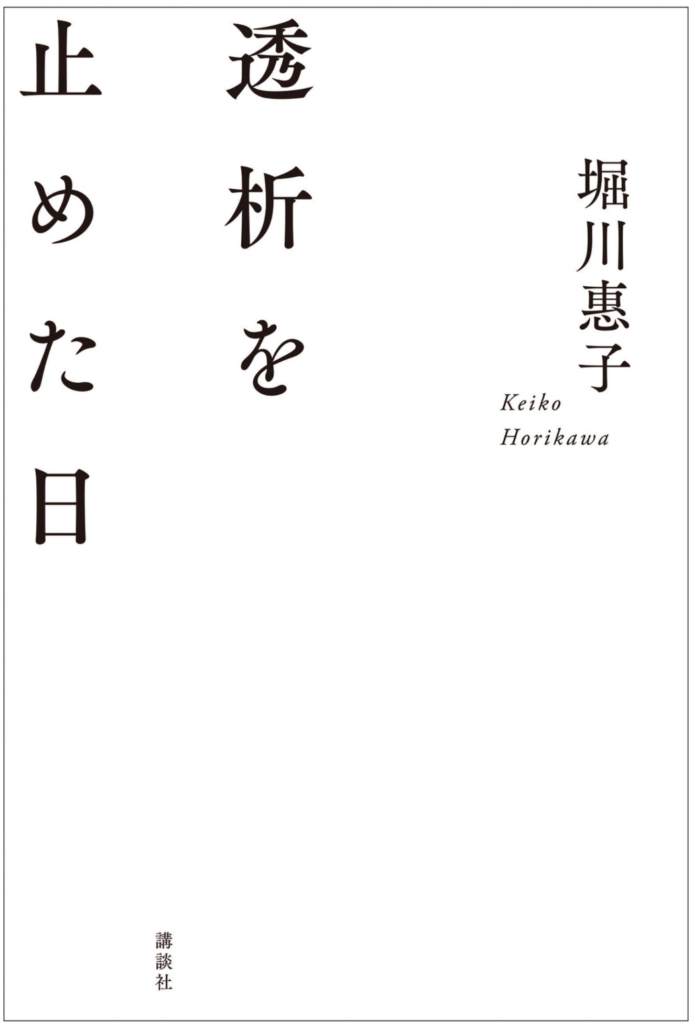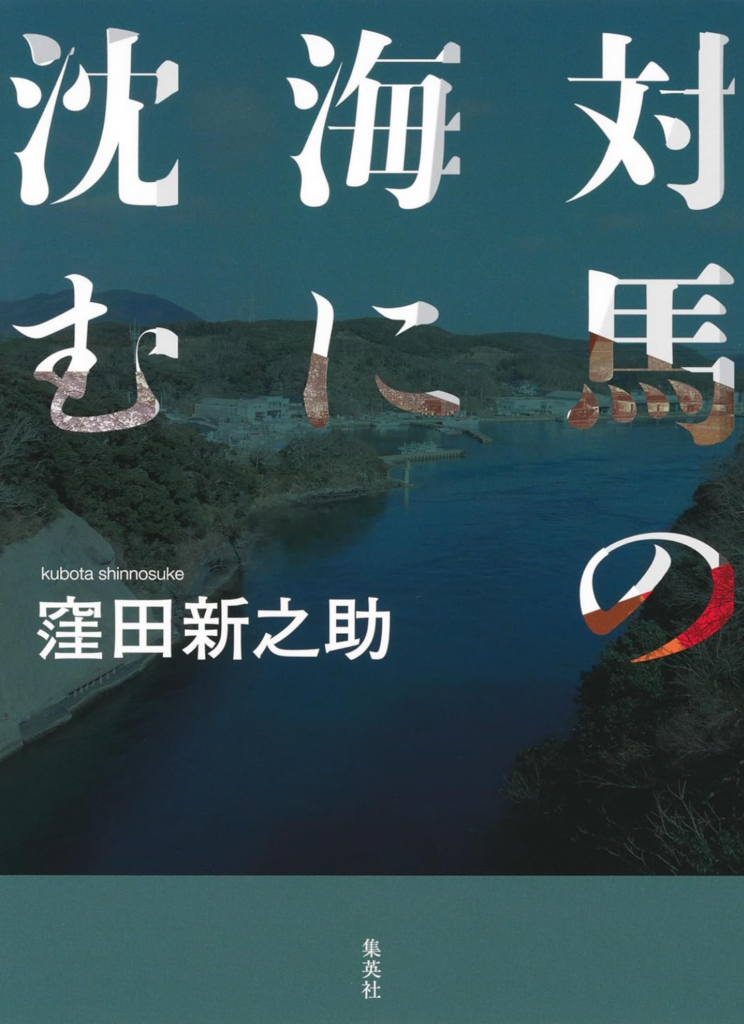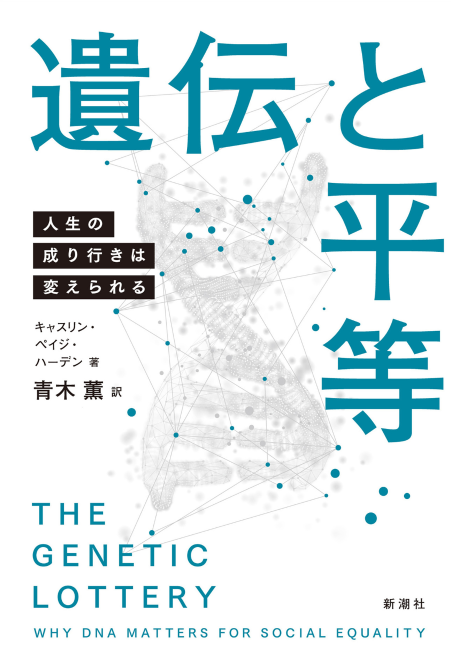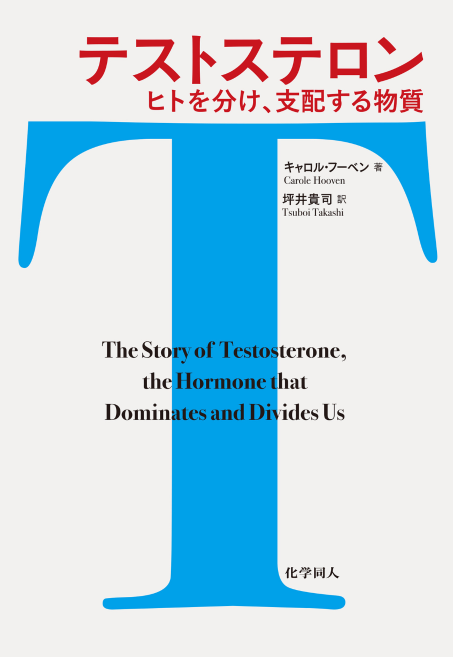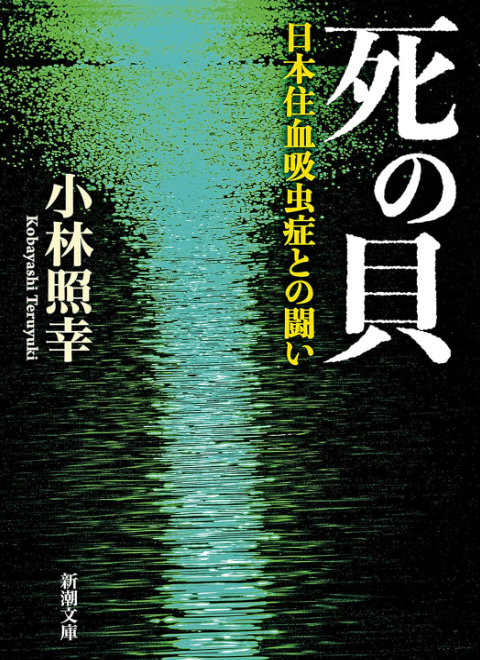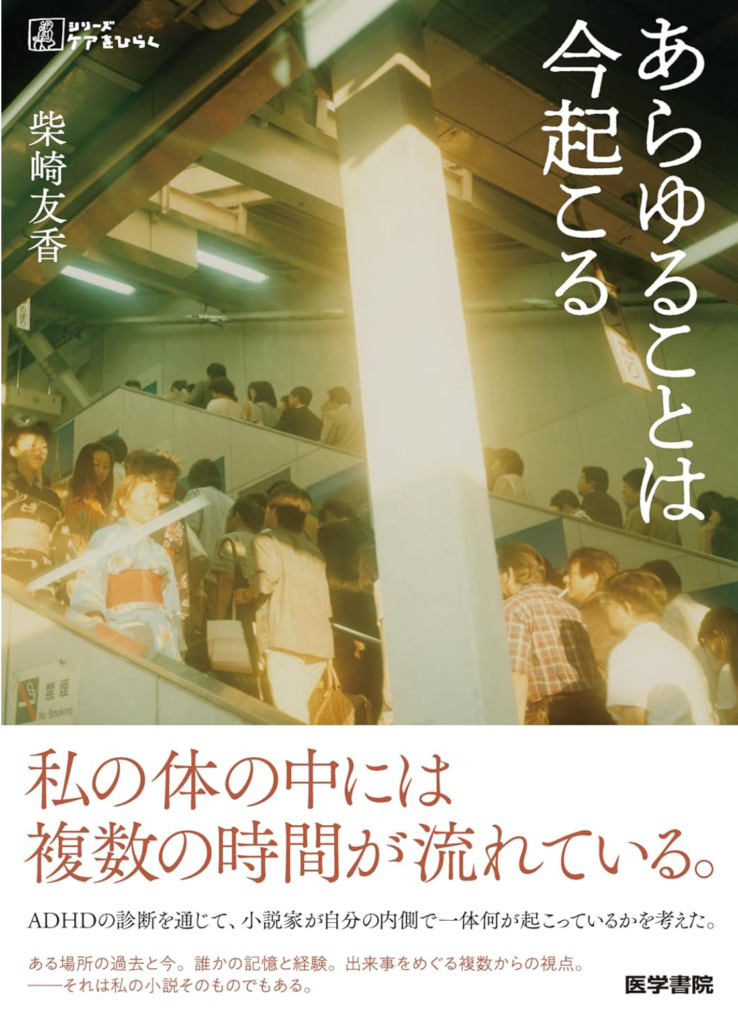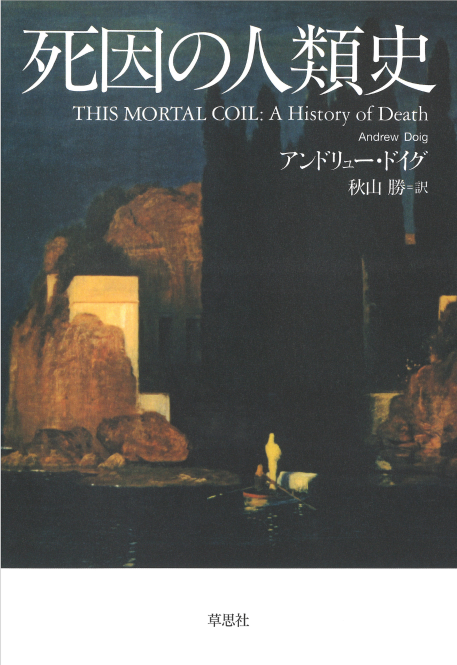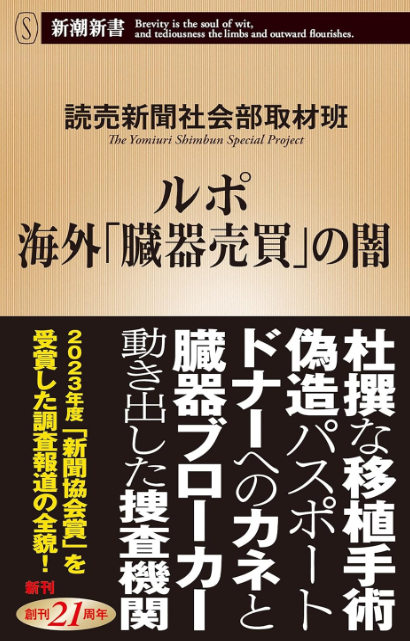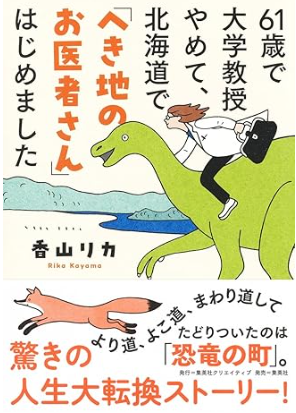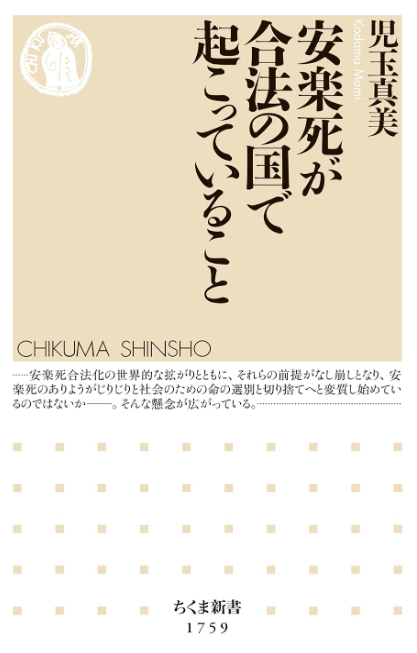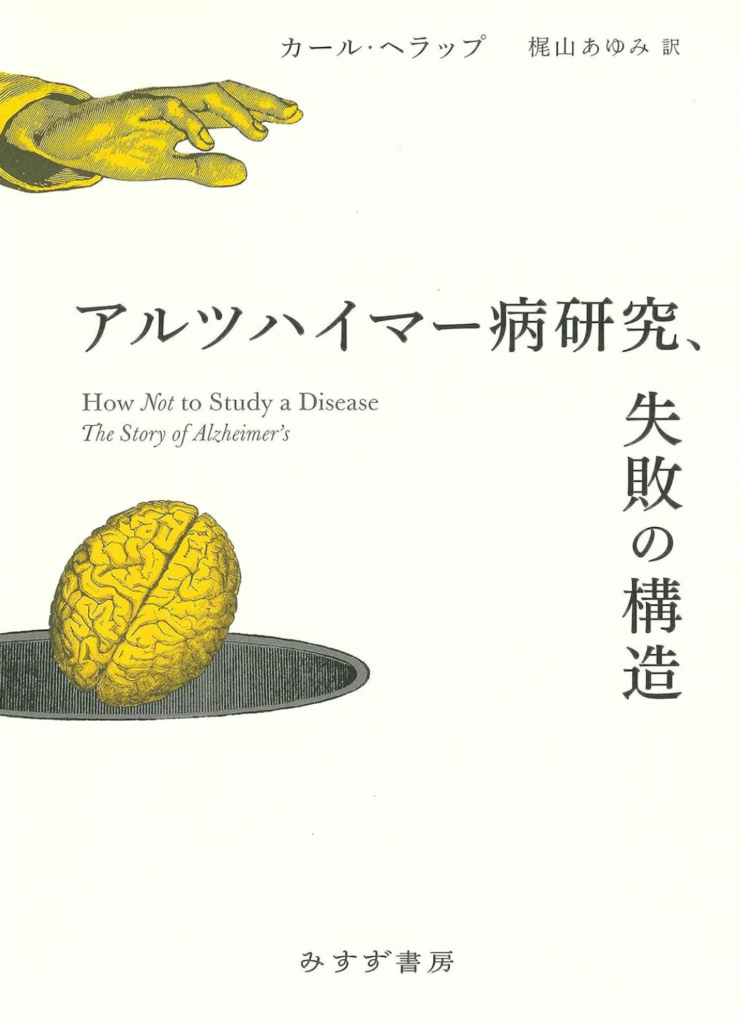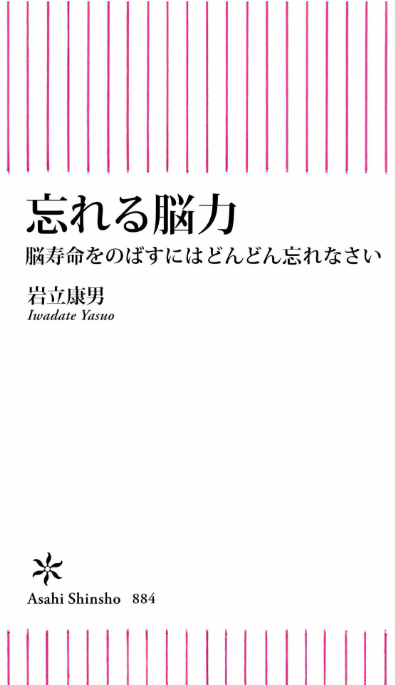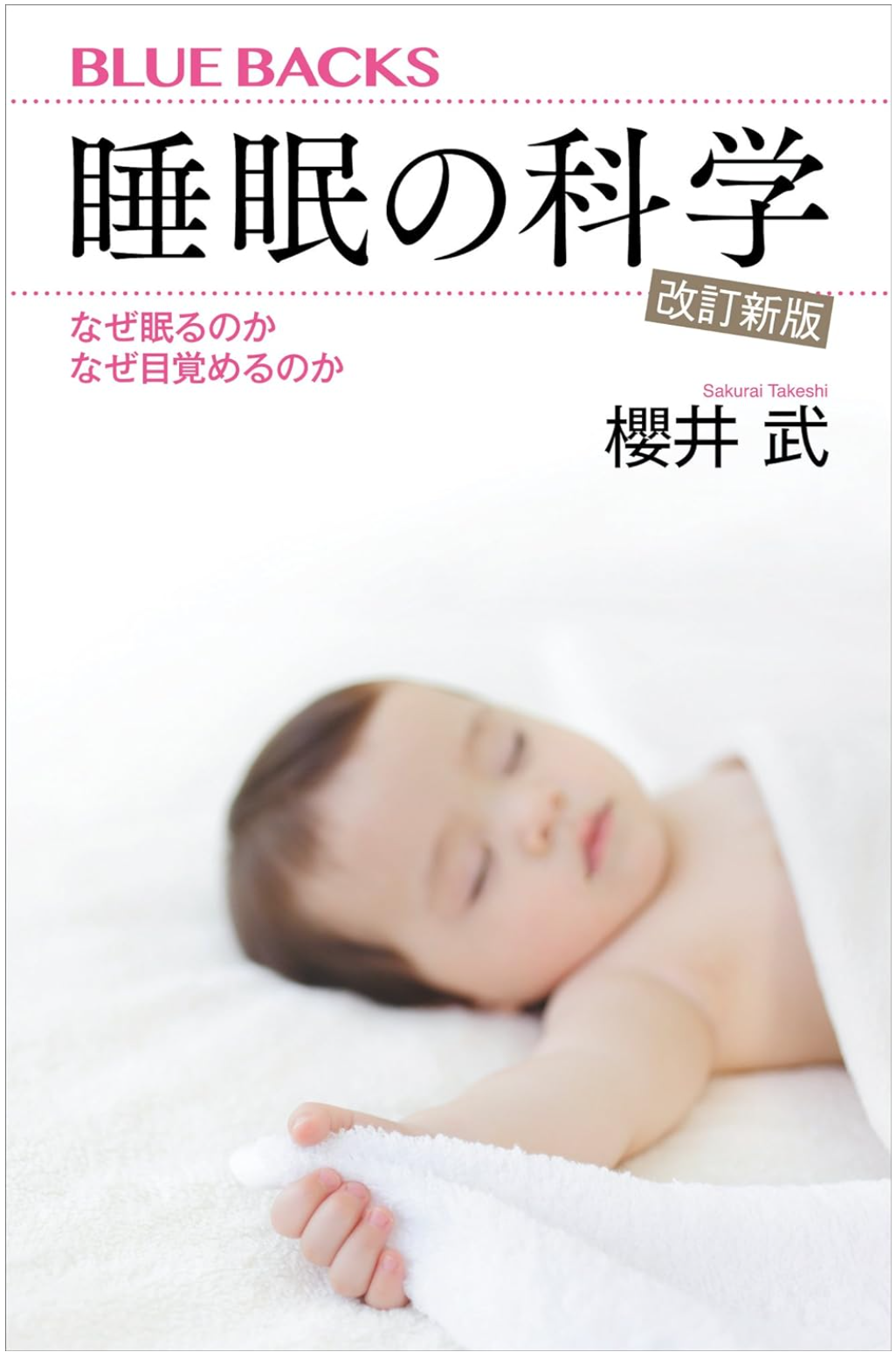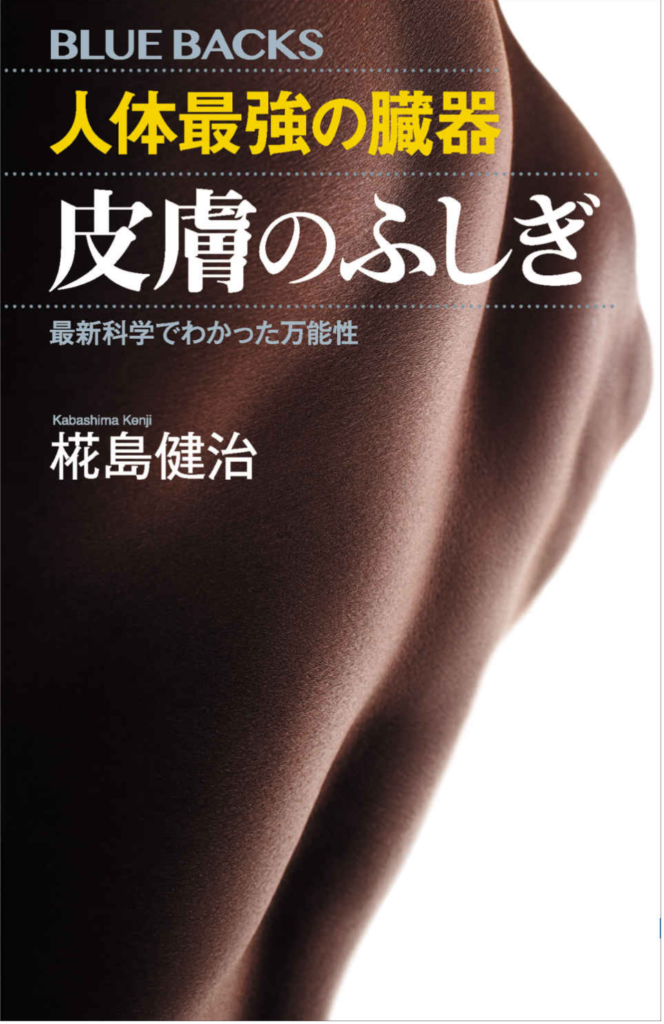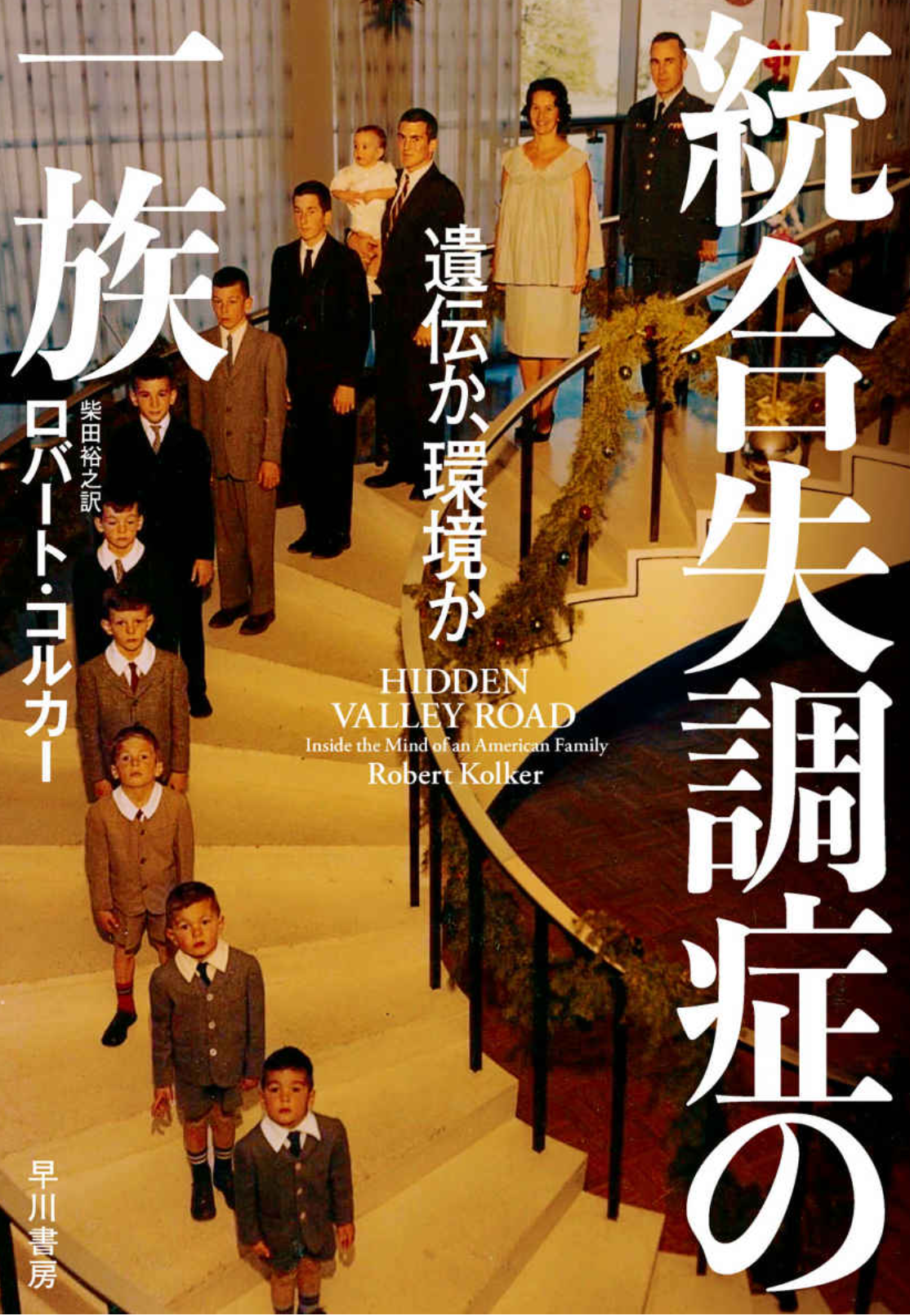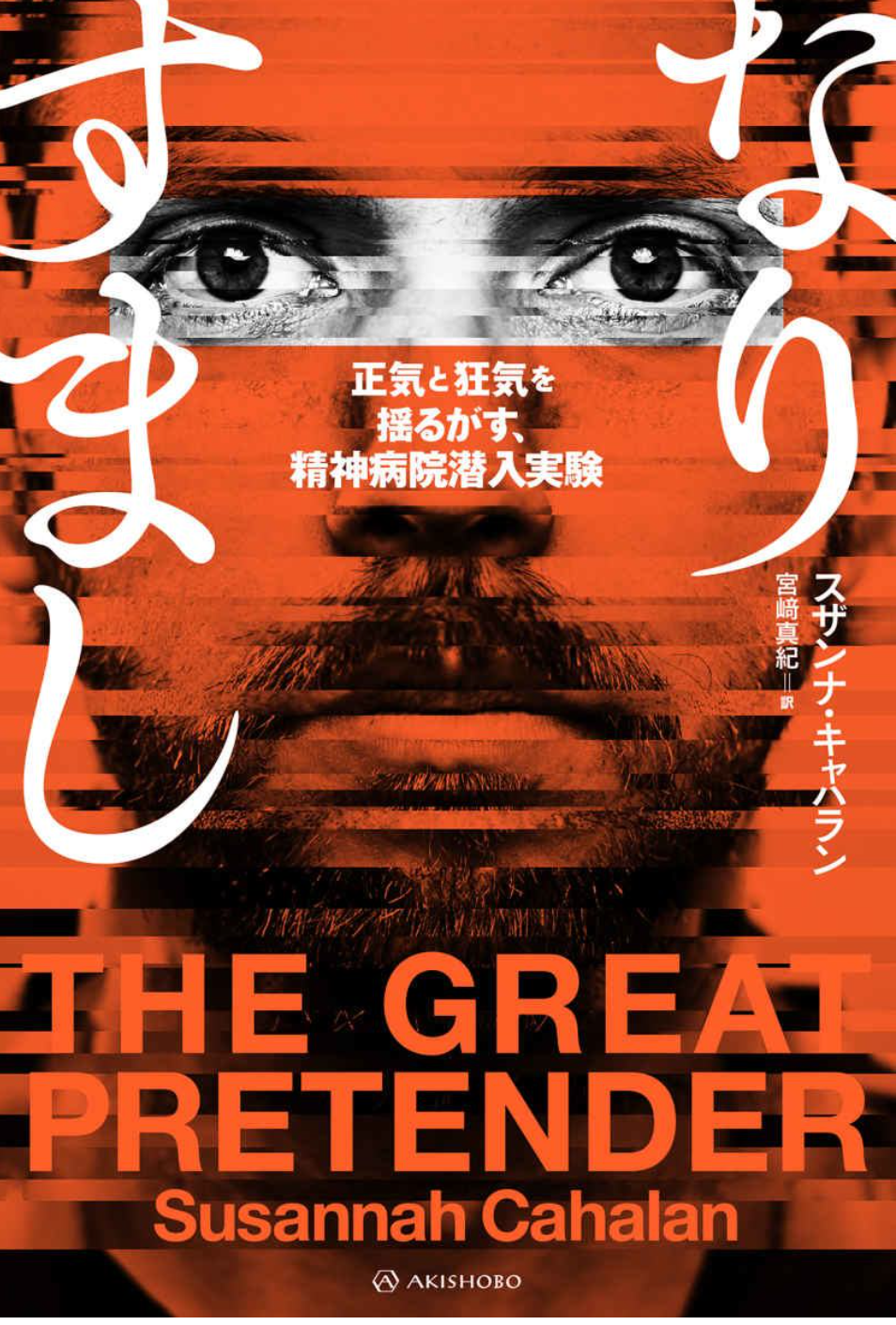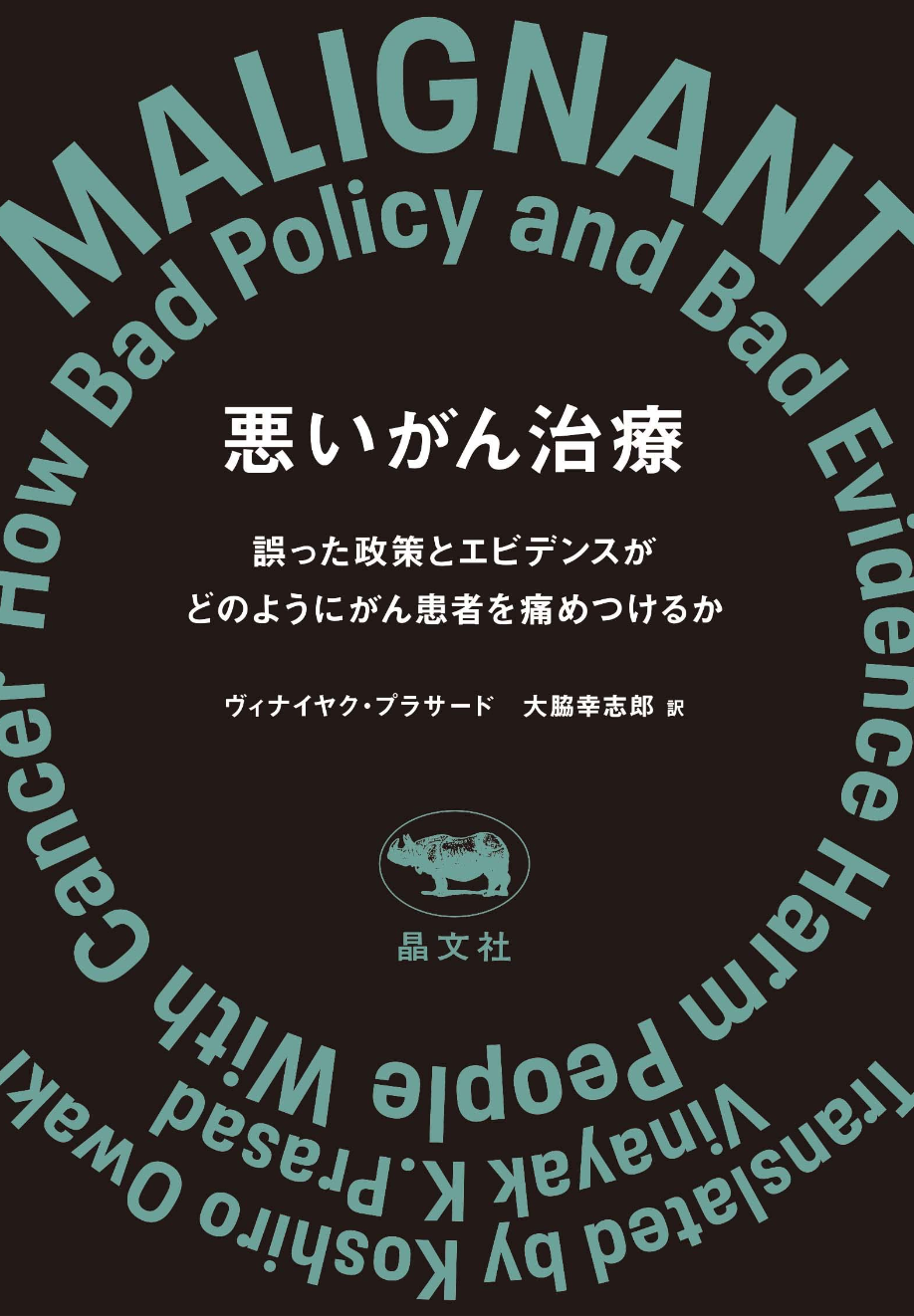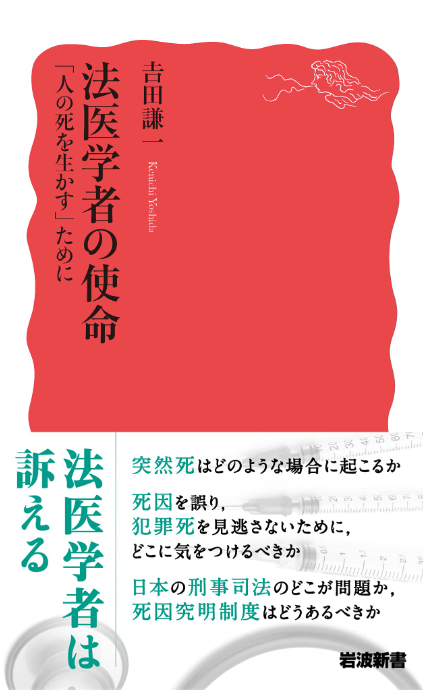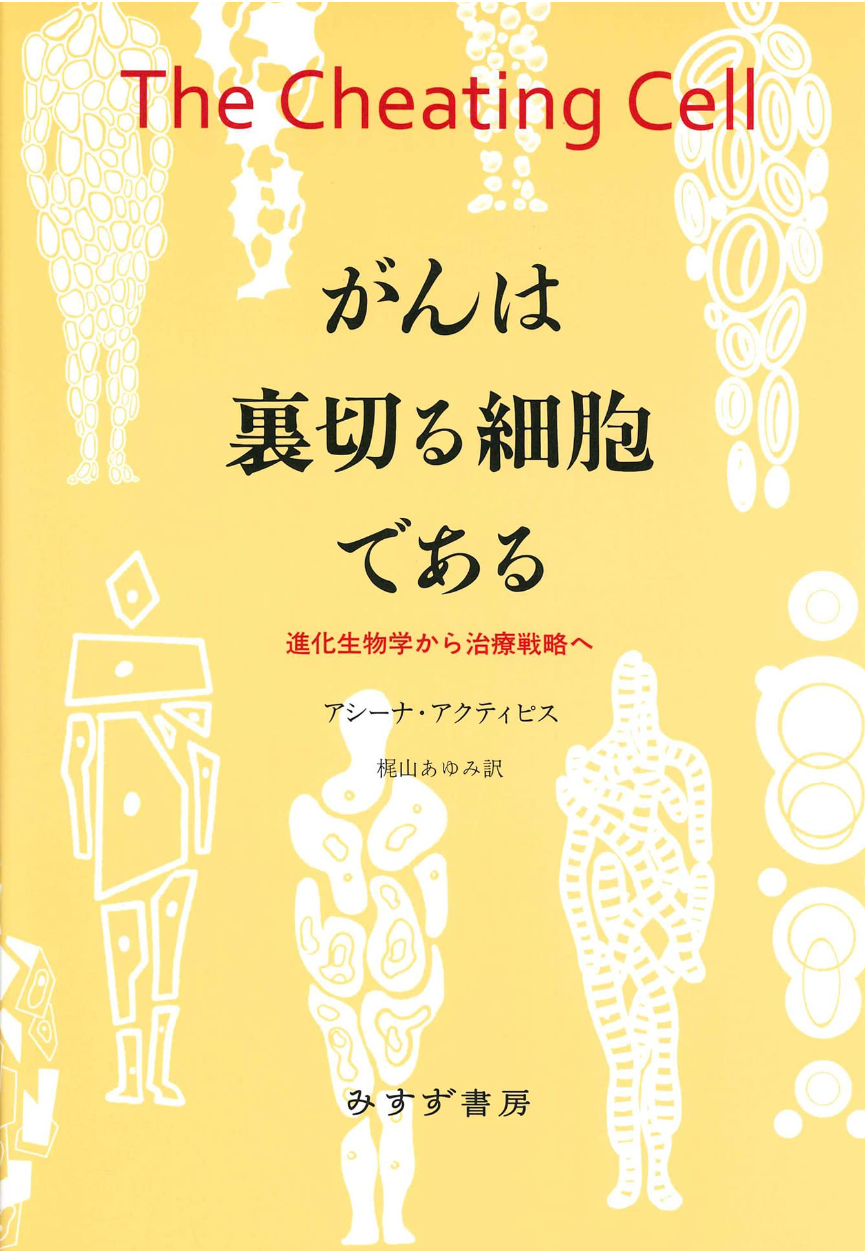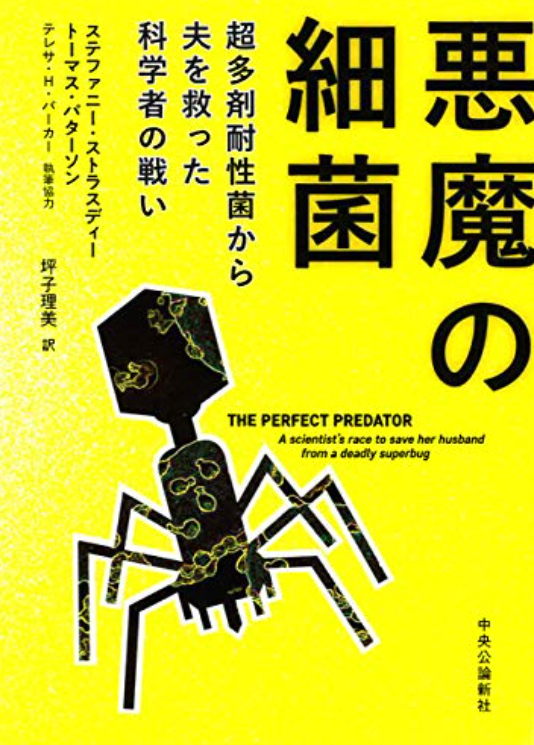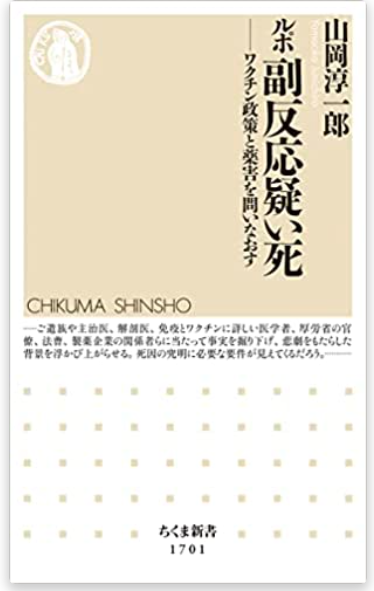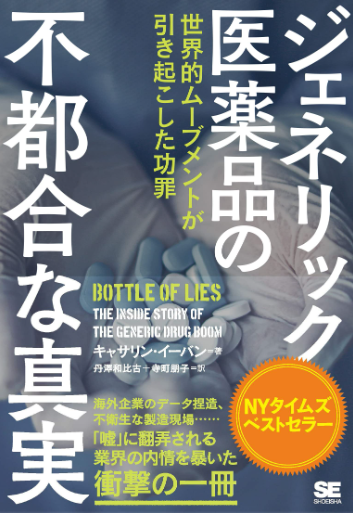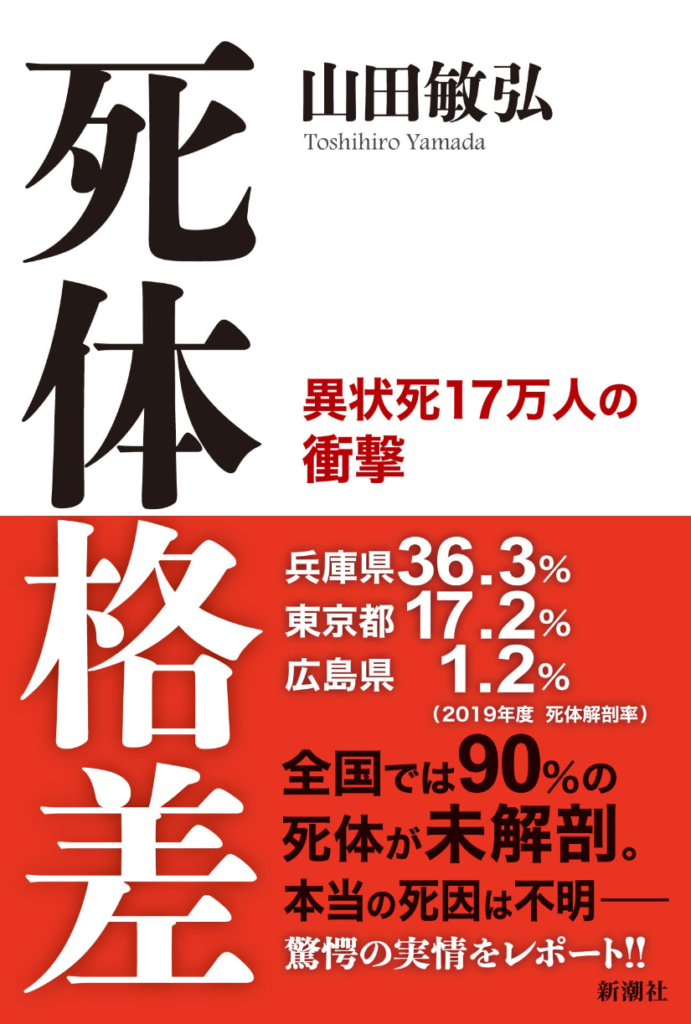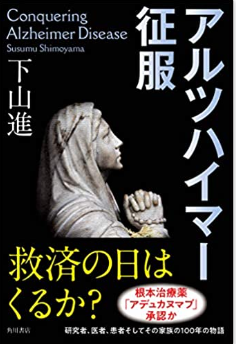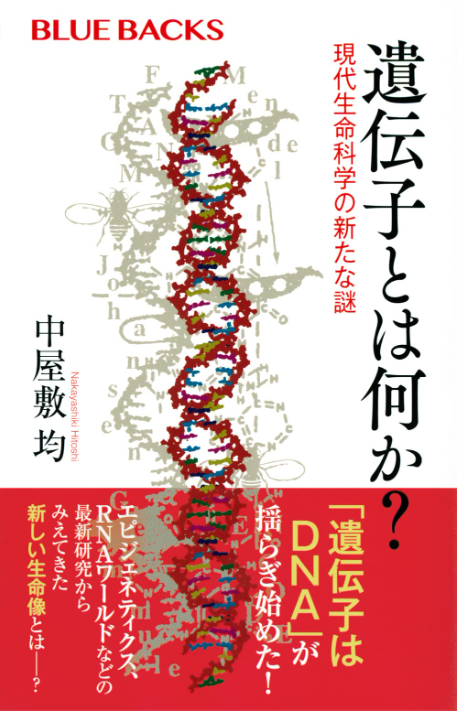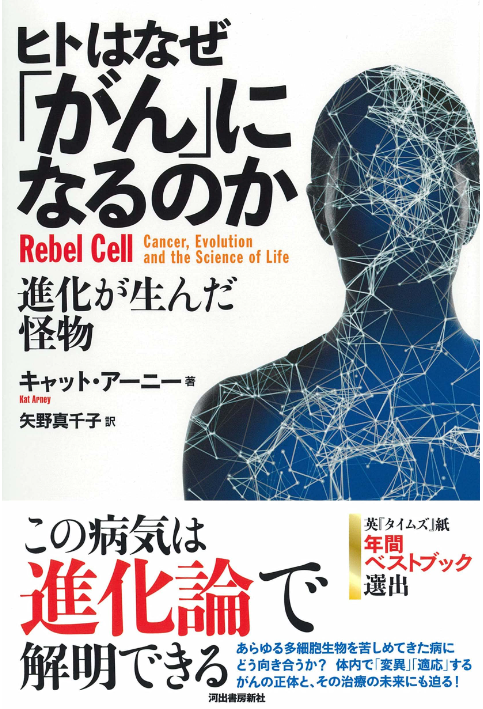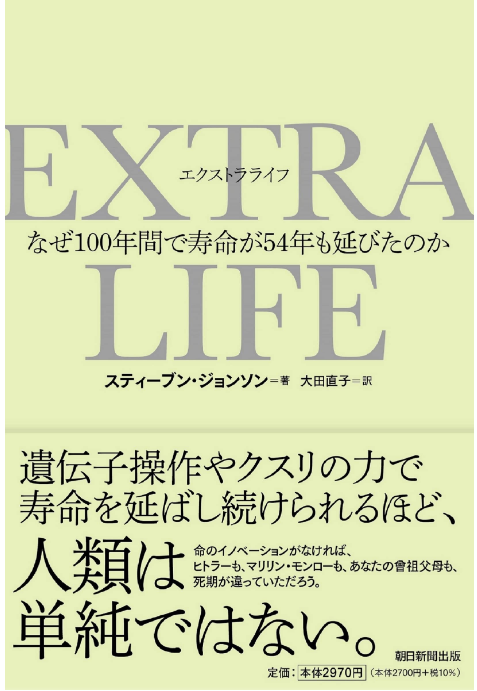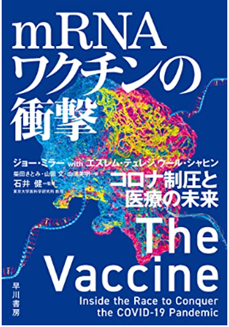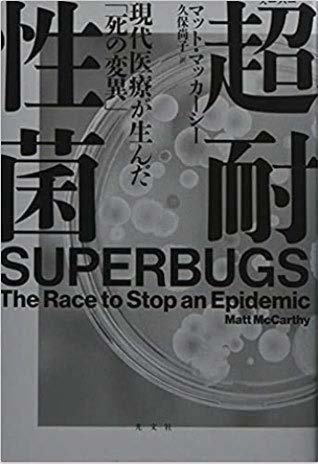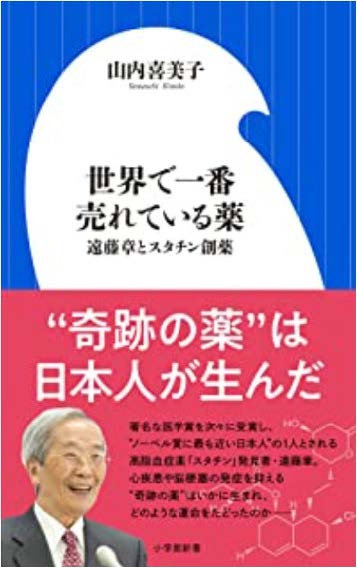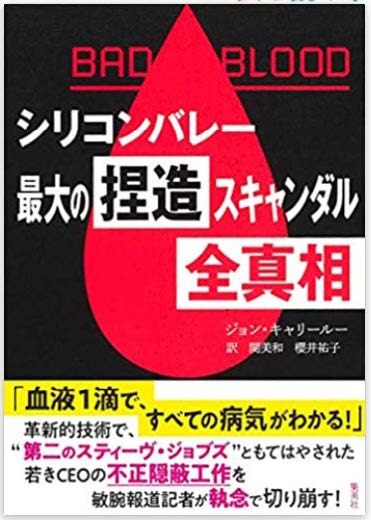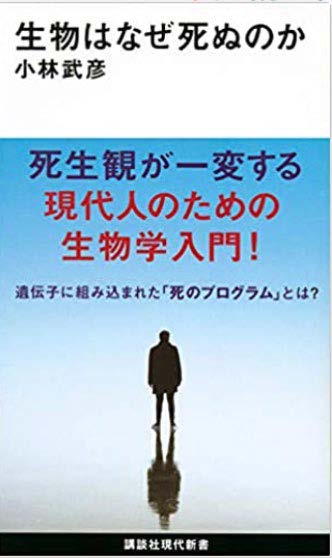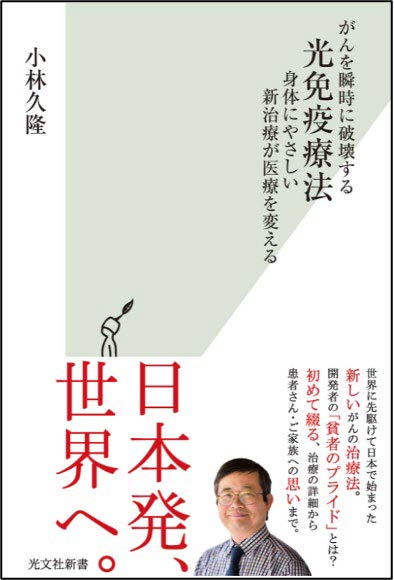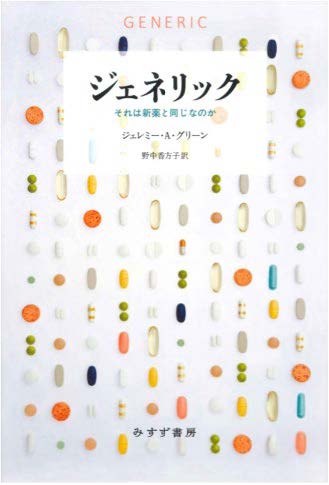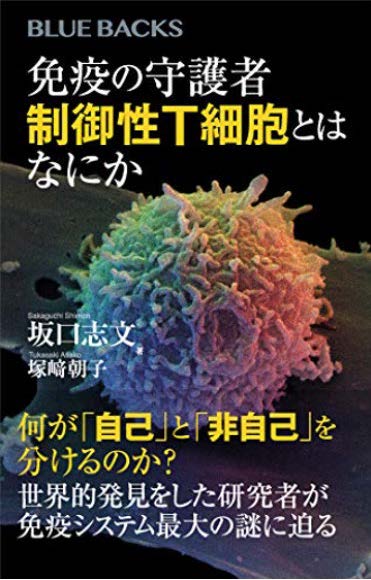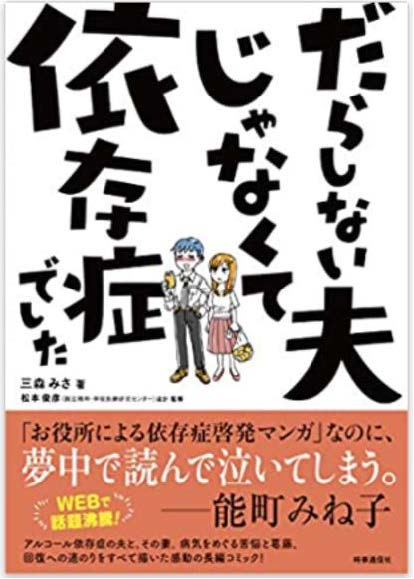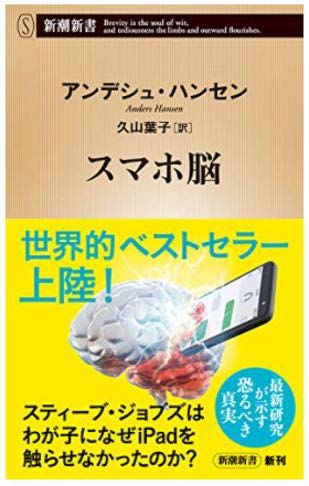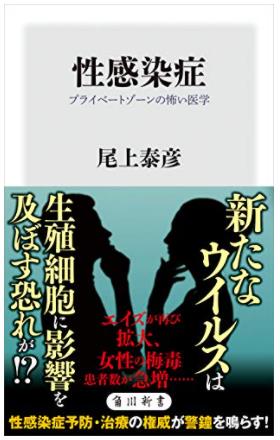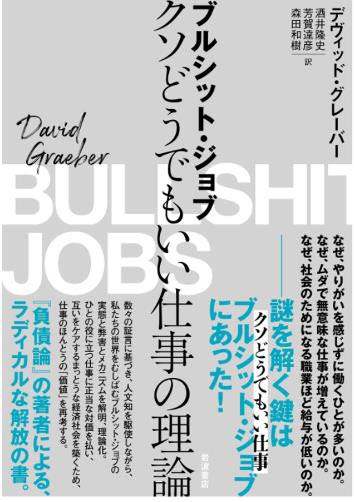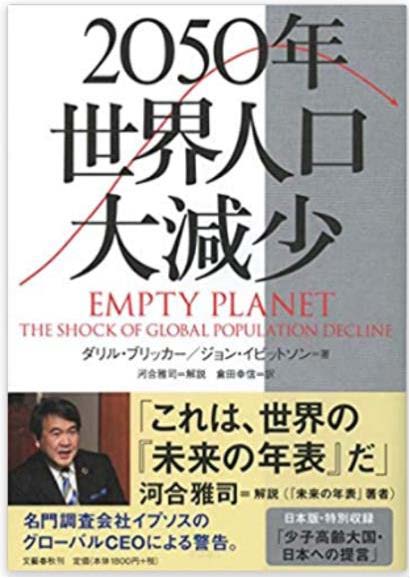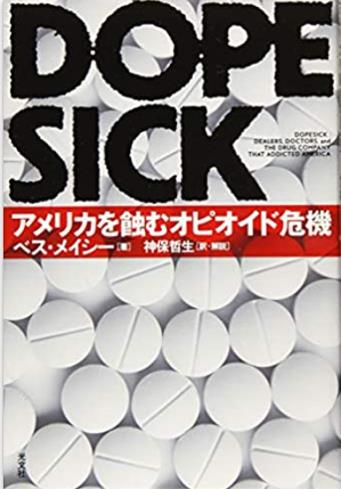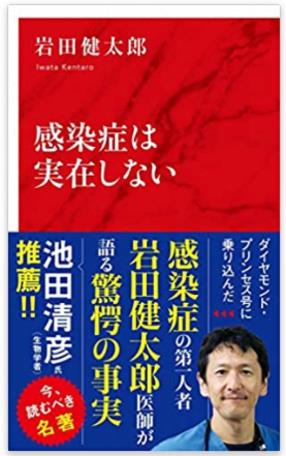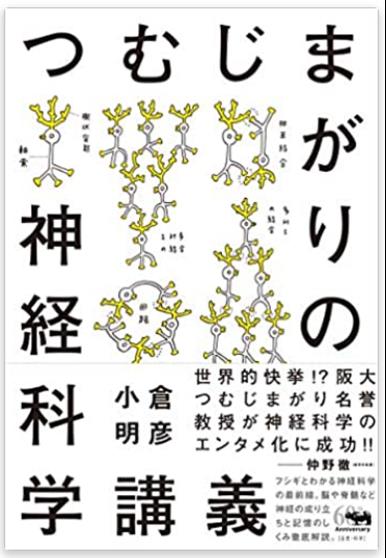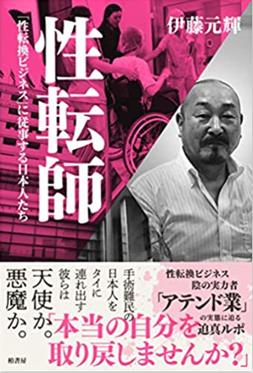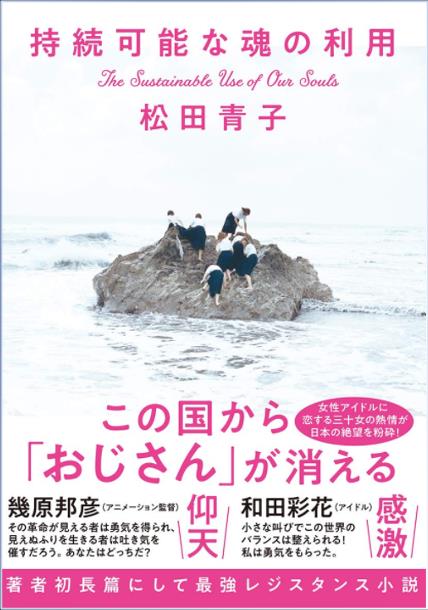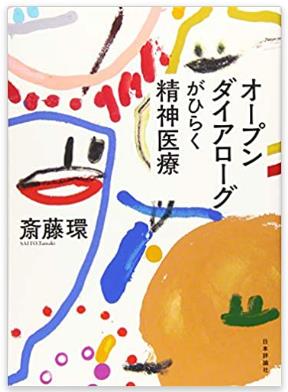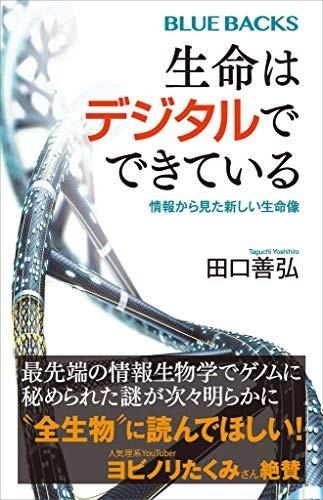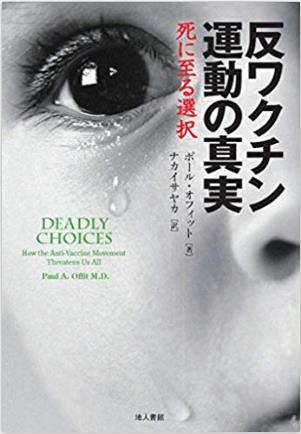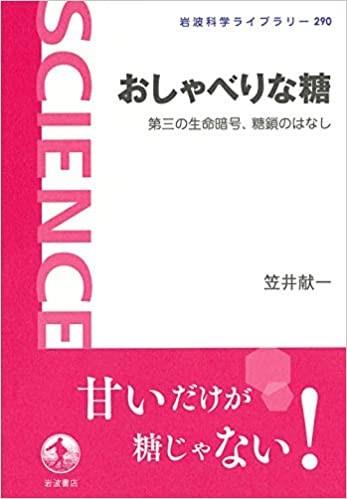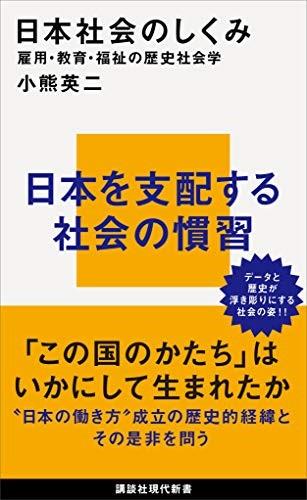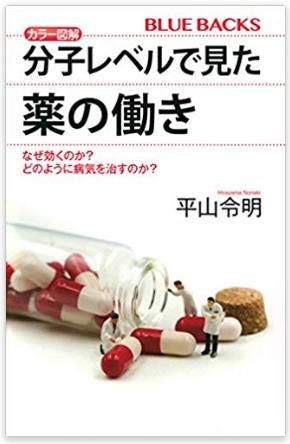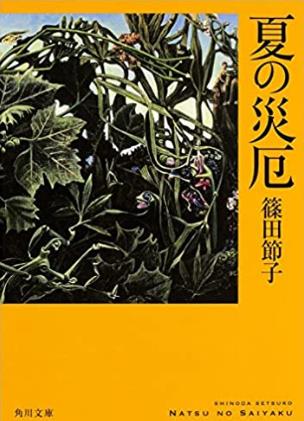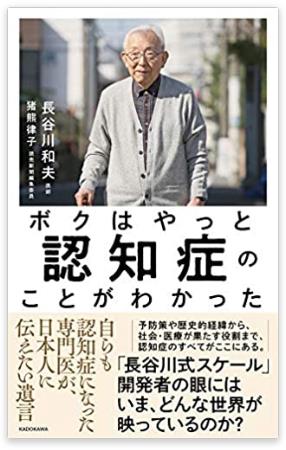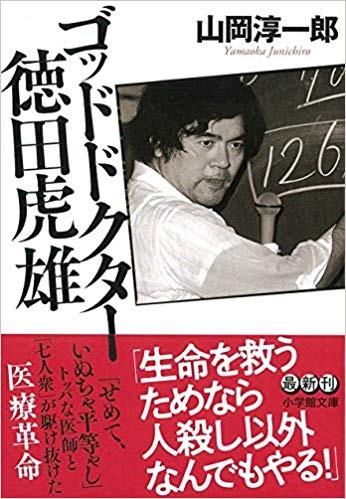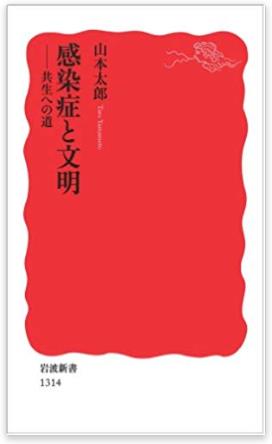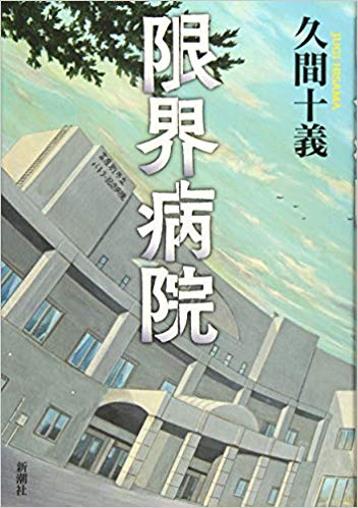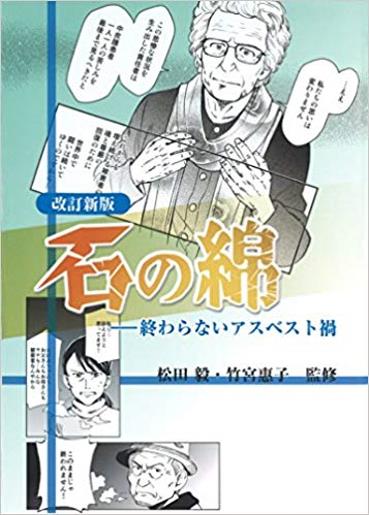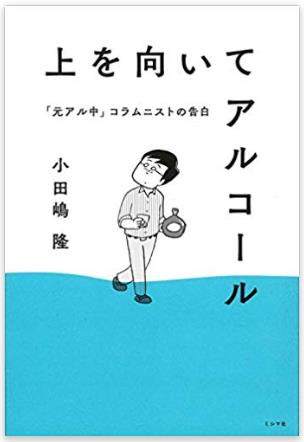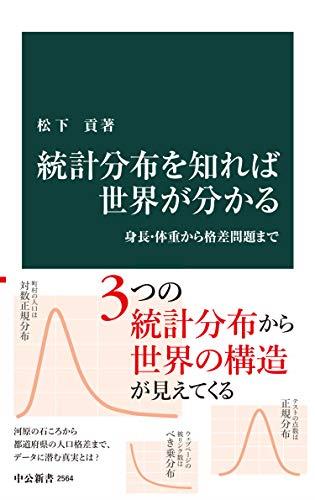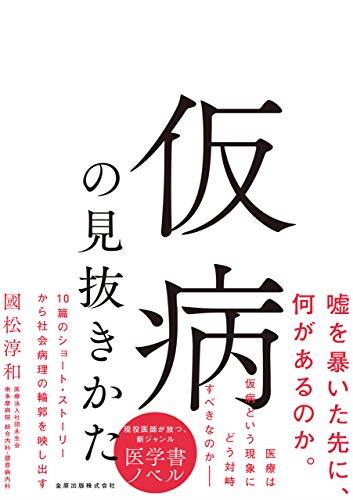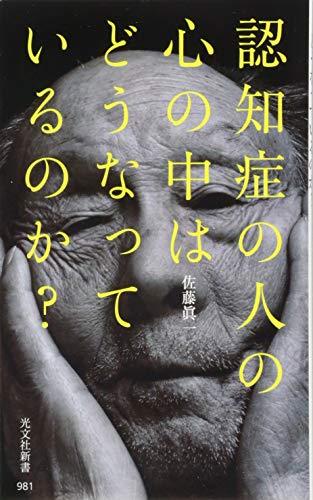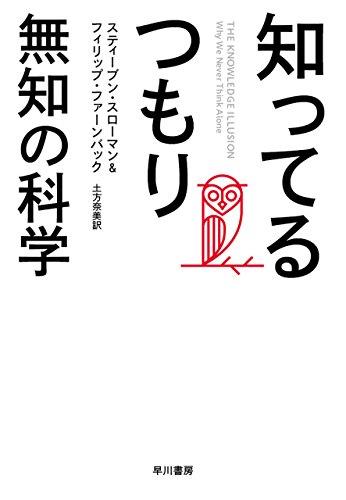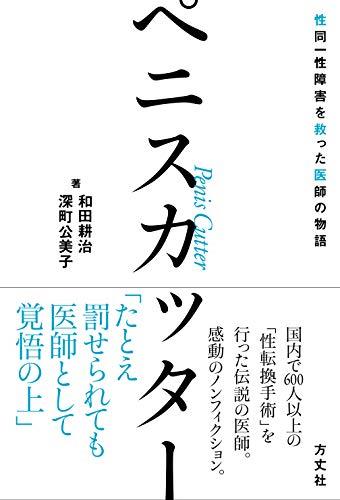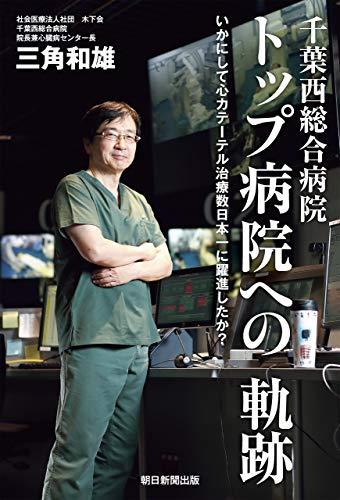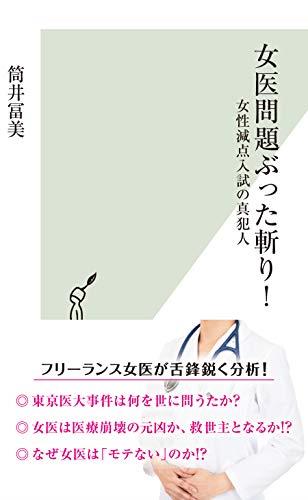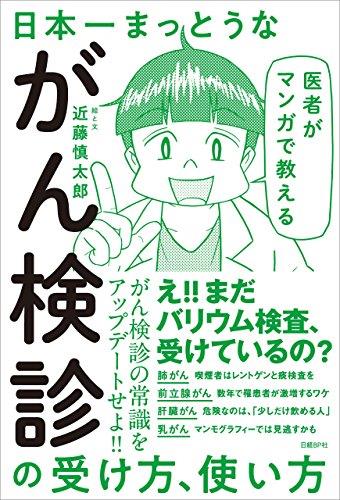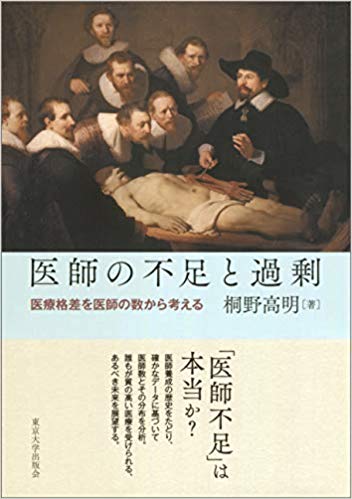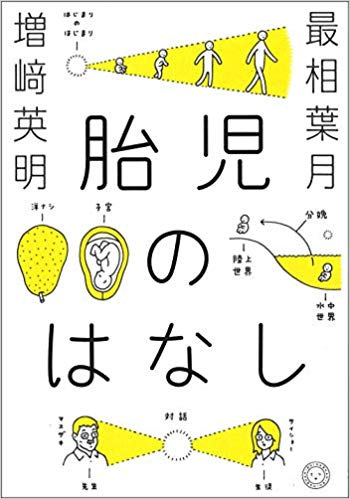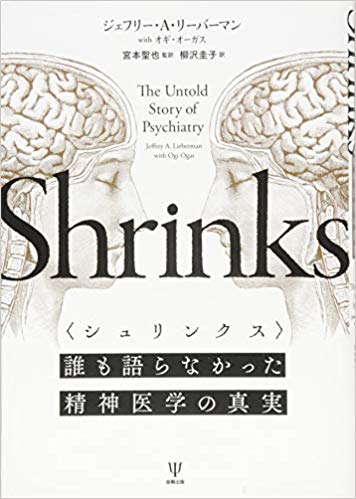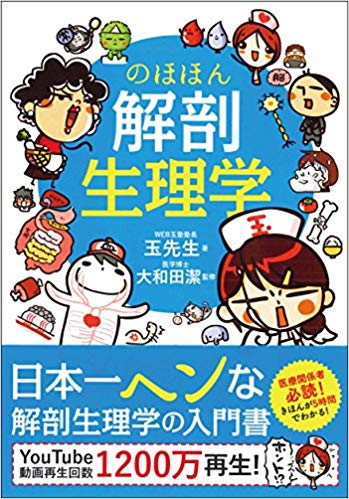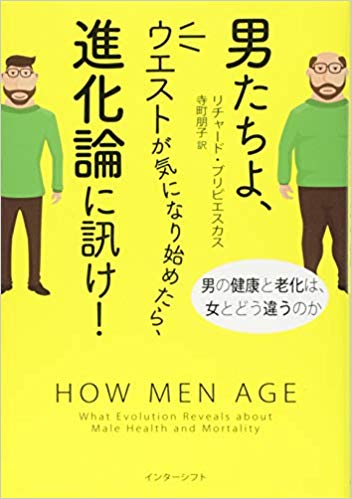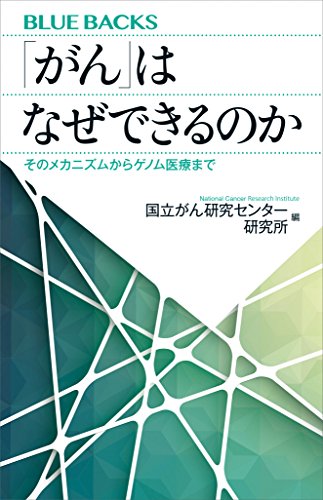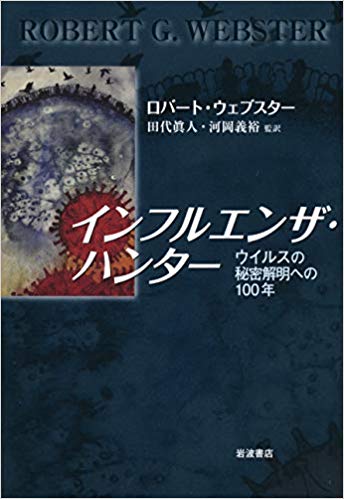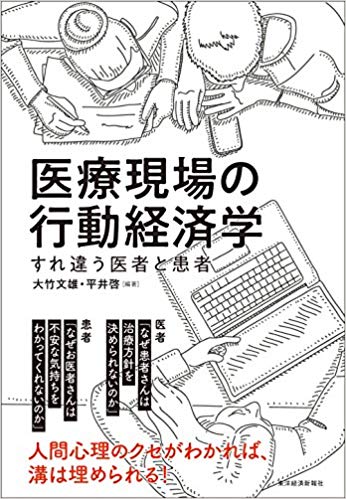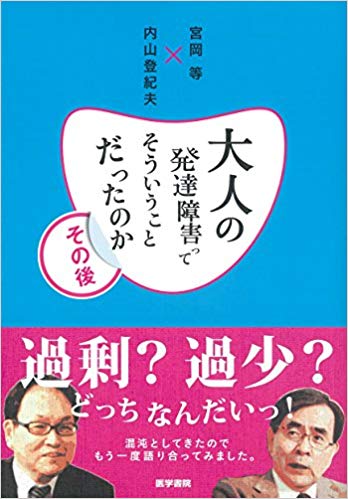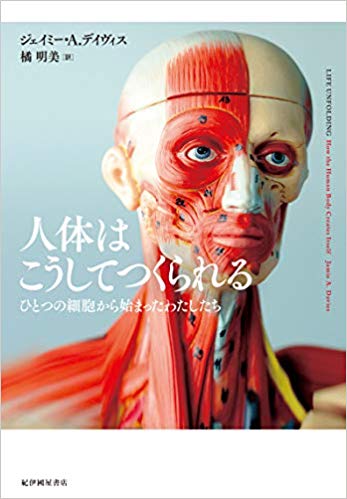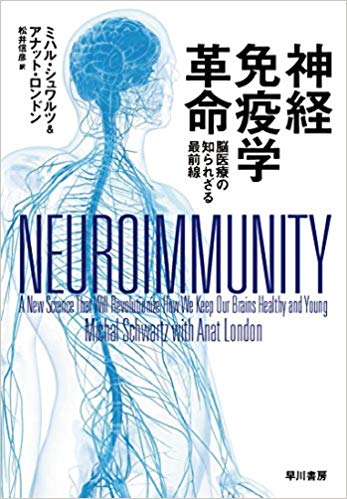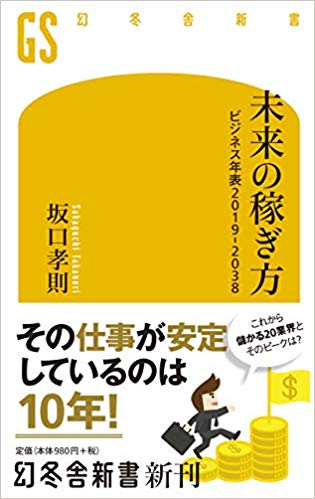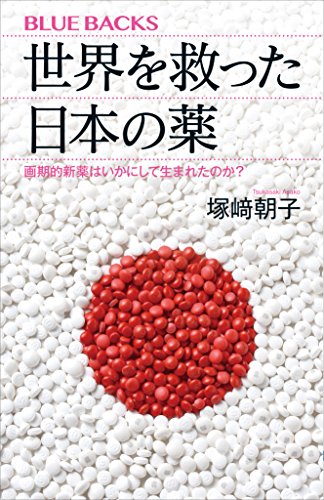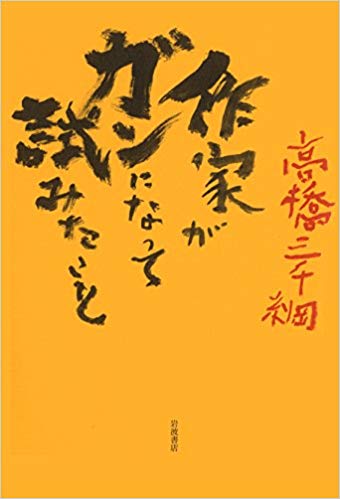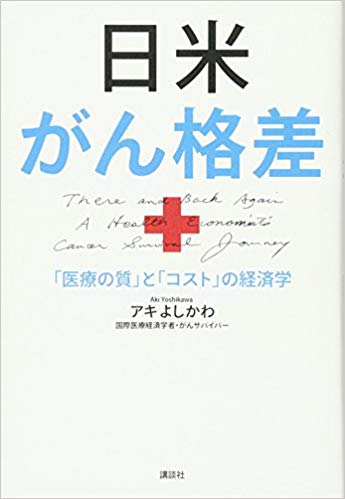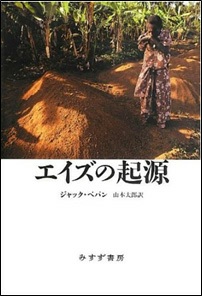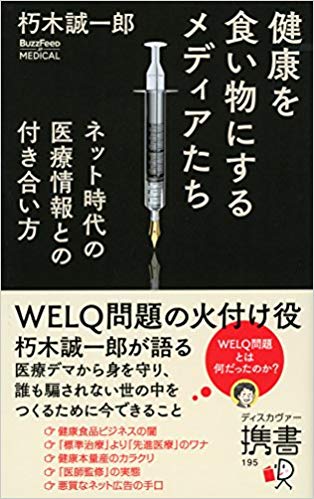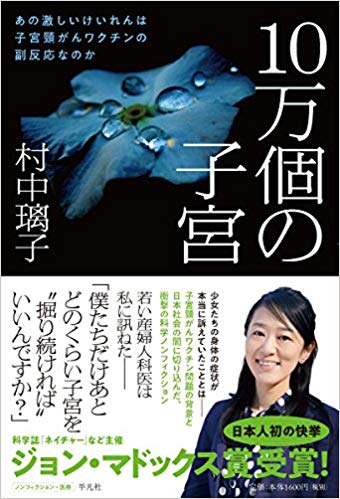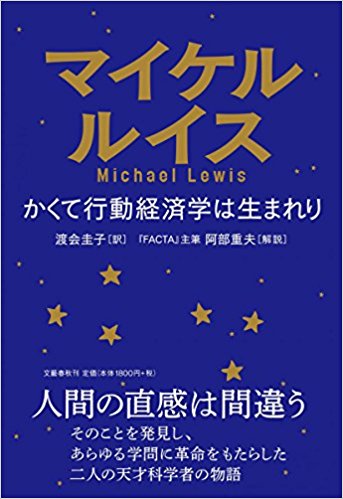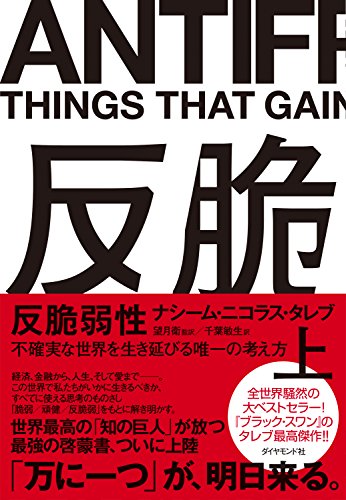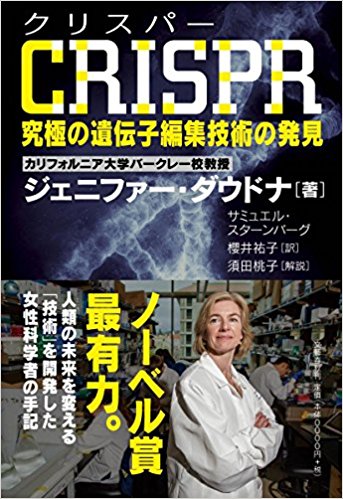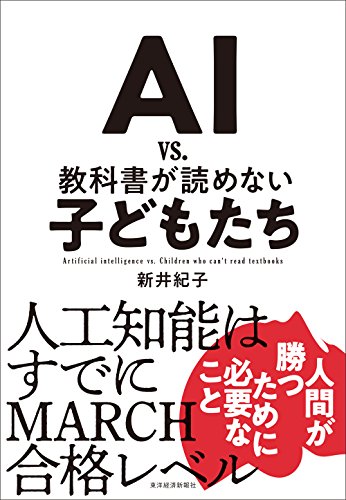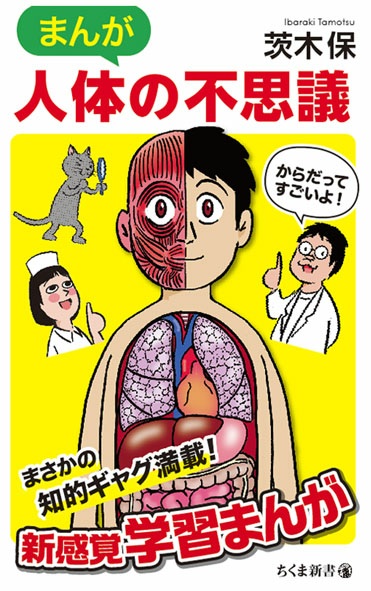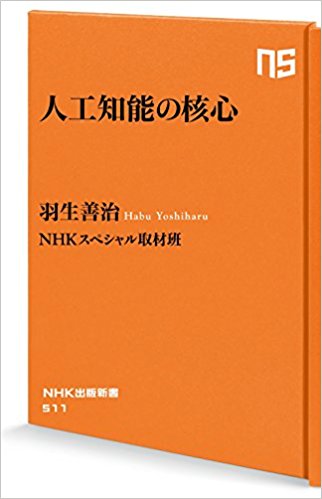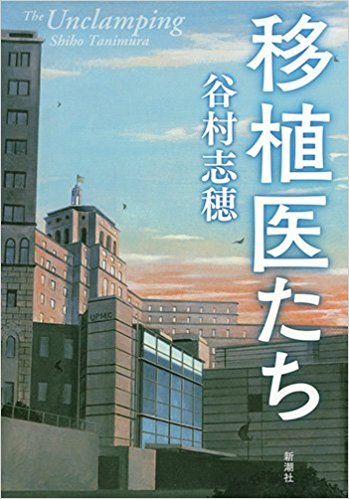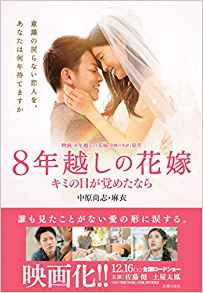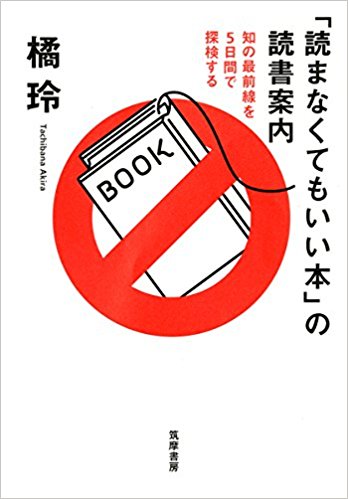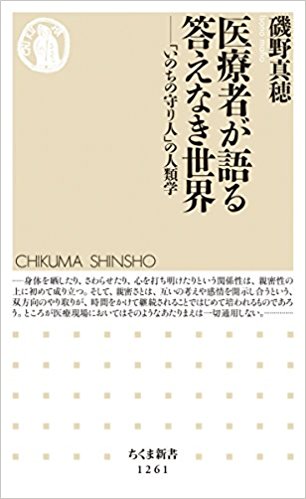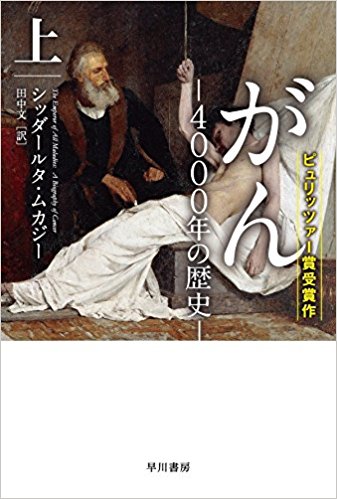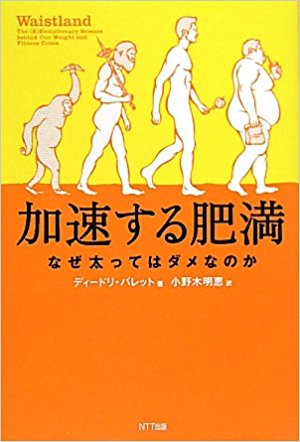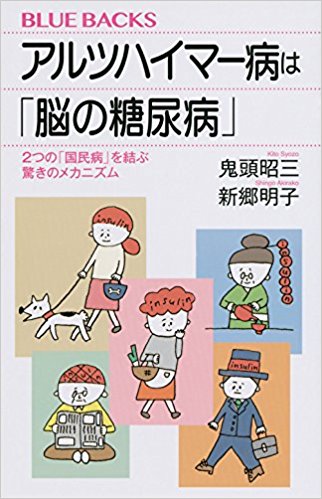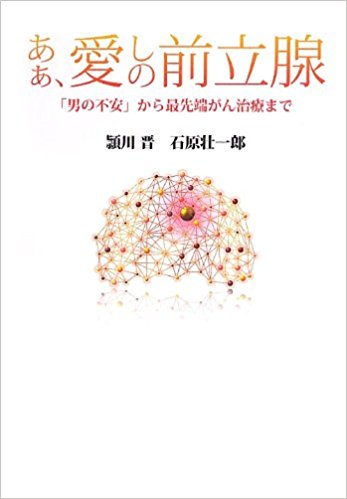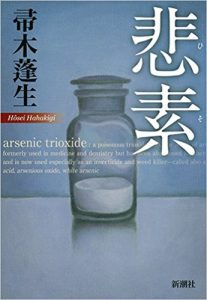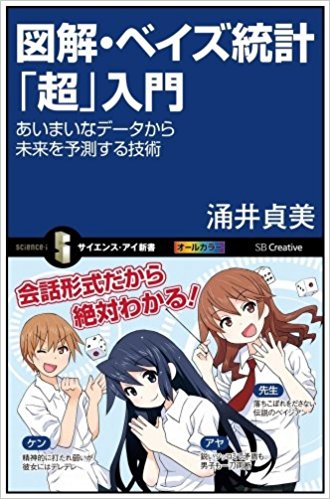査定に役立つブックガイド
元外科医。生命保険のアンダーライティング歴25年。そろそろ前期高齢者。
告知や診断書を見ているとアンダーライティングは常に最新の医療現場と直結していることを実感しますよね。そんな最新医学をキャッチアップしたいと本を読み続けています。そうした読書の中から医師ではなくても「これは面白い!」と思える本をレビューしていきます。レビューだけで納得するもよし、実際に読んでみるもよし。お楽しみください。
読書以外ではジャズ(女性ヴォーカル好き)を聴いたり、大ファンである西武ライオンズの追っかけをやってみたり。ペンネームのホンタナは姓をイタリア語にしたものですが、「本棚」好きでもあるので・・ダジャレで。
ブックガイド(最新号)
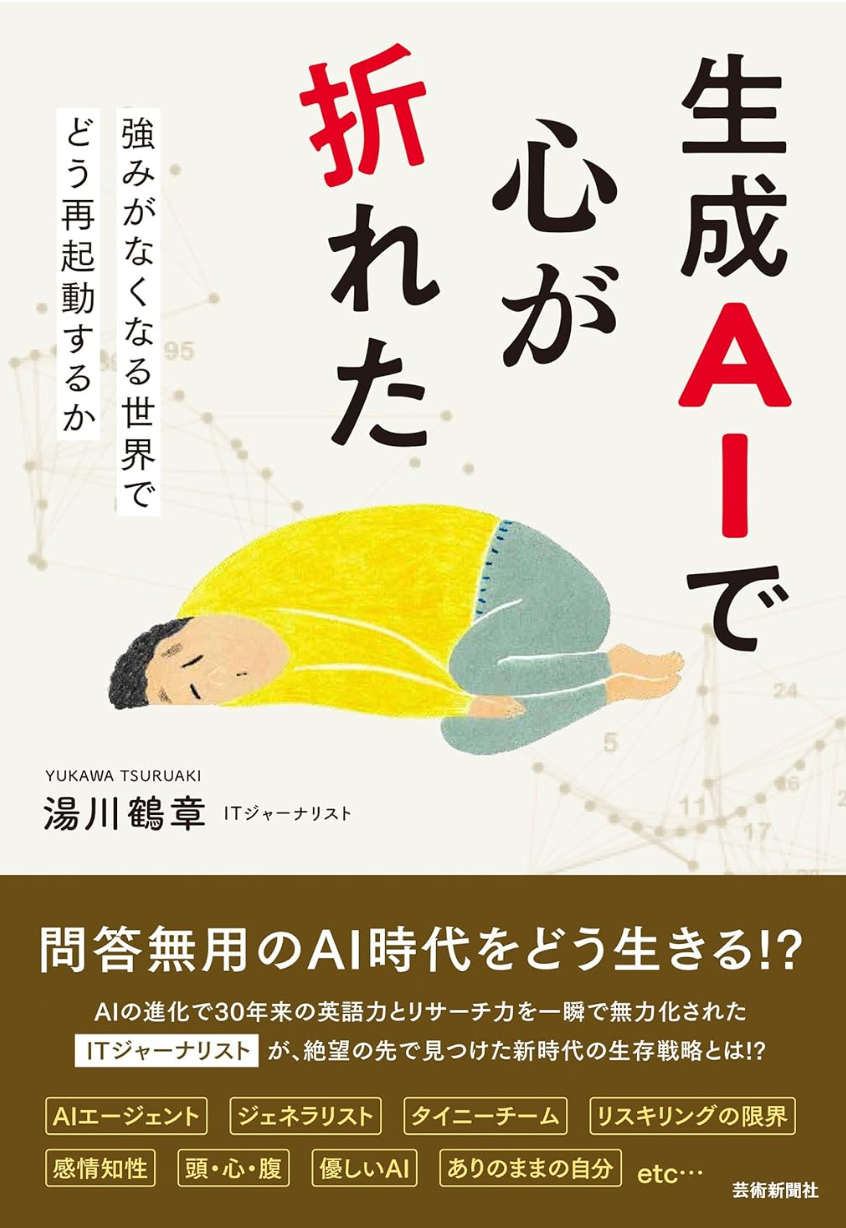
ーーやがて悲しきーー
生成AIで心が折れた
強みがなくなる世界でどう再起動するか
湯川鶴章 著
芸術新聞社 税込定価1980円 2025年12月刊行
「気楽に読めて、査定力もアップする本を!」というコンセプトのブックガイド。2026年の幕開けを飾る第144回は、ちょっと刺激的な一冊から。世の中、猫も杓子も「生成AIですごいことができる!」「乗り遅れるな!」の大合唱です。そんなAI礼賛の時代に、書店で思わずぎょっとするタイトルの本を見つけました。その名もズバリ、『生成AIで心が折れた』。
著者の湯川鶴章氏はシリコンバレーの黎明期から現地のハイテク産業を見つめ続けてきた、知る人ぞ知るベテランITジャーナリストです。そんな玄人の彼が、なぜ「心が折れた」のか? このタイトルに惹かれて手に取ると、そこには意外なほど率直な「敗北の記録」がありました。
本書の前半では、著者が長年積み上げてきた「英語力」や「リサーチ力」といったスキルが、AIの進化によって一瞬で無価値化(コモディティ化)されていく様が、痛切な懺悔とともに語られます。一生懸命AIの最新情報を学んでも、その学習コストを回収する前に、AI自体の進化がその知識を陳腐化させてしまう。まさに「いたちごっこ」の徒労感。私たちのアンダーライティングもまた、専門知識を武器とする知識労働者である以上、この感覚は他人事ではありません。
本書を読みながら、ふと私の脳裏をよぎったのは、かつてのイギリス産業革命の歴史です。当時の綿織物産業でも、新しい紡績技術が導入されるたびに、先行者は莫大な利益を得ました。しかし、その技術が拡散し一般的になると、利益は急速に消失し、工場主たちはまた次の技術革新へと駆り立てられました。
現在のAI革命も、これと全く同じ構造にあります。「AIですごいことができる!」と飛びついても、その技術が民主化された瞬間、先行者利益は霧散する。今、時代の寵児としてもてはやされているAI技術者やデータサイエンティストでさえ、その技能がコモディティ化し、没落するまでの時間はそう長くはないのかもしれません。
著者が吐露する「心が折れた」という感覚は、この逃げ場のない無限競争への疲弊感に他ならないのです。では、どうすればいいのか?
著者は本書の後半で、その答えを「内なるOSのアップデート」、すなわちマインドフルネスやヨガといった精神性、あるいは「心」のあり方に求めます。実はここが、本書の評価が分かれるポイントかもしれません。「結局、精神論か」と。
確かに、私たちのような実務家からすれば、ヨガをしたところで明日の査定業務が減るわけでも、AIの脅威が消えるわけでもありません。しかし、著者が精神世界に救いを求めたこと自体が、今のAI革命がいかに「論理的な解決策が見当たらない」フェーズにあるかを逆説的に証明しているようにも思えます。
産業革命の荒波が落ち着き、新たな社会構造(ポストAI時代)が定着するまで、世界はまだしばらく混乱の中にあり続けるでしょう。その「答え」が出るまでの間、私たち現場の人間はどう振る舞うべきか。
私は、著者のように「心が折れる」ことを認めつつも、やはりこの「いたちごっこ」を続けるしかないのだと感じています。たとえすぐに陳腐化すると分かっていても、目の前のAIツールを使いこなし、わずかな期間の「先行者利益」を拾い集め続ける。今は泥臭く、そのサイクルを回し続けることこそが、唯一の生存戦略なのかもしれません。
「生成AIで心が折れた」。そのタイトルに嘘はありませんが、折れた心のまま、それでもキーボードを叩き続けるしかない。そんな諦念と覚悟が入り混じる、2026年の始まりにふさわしい一冊です。(査定職人ホンタナ Dr. Fontana 2026年1月)
リンク 👉 著者の「心が折れた」告白動画はこちら