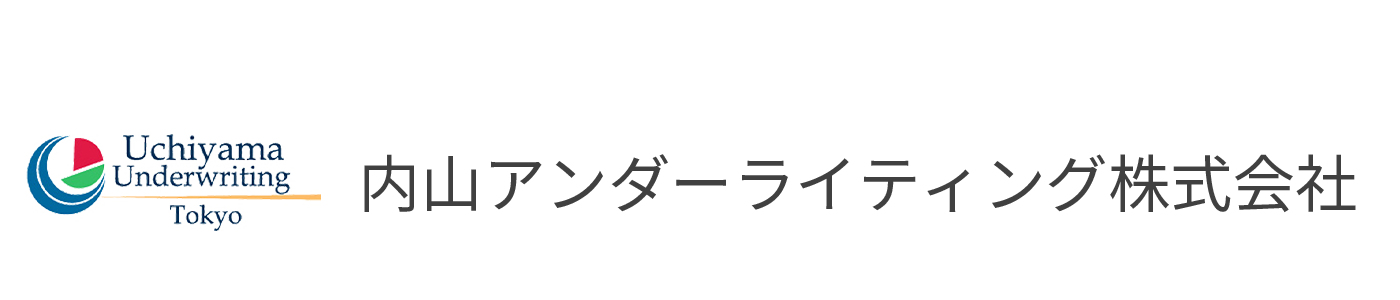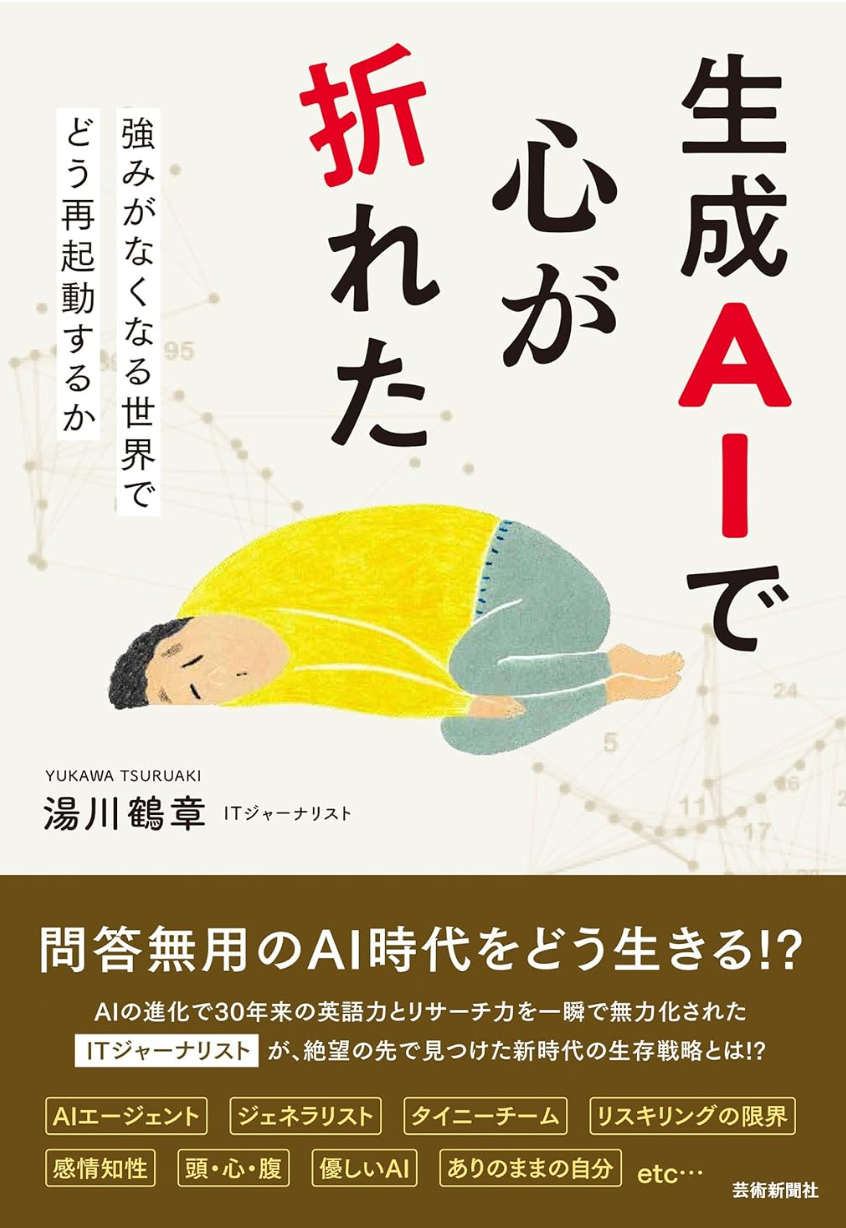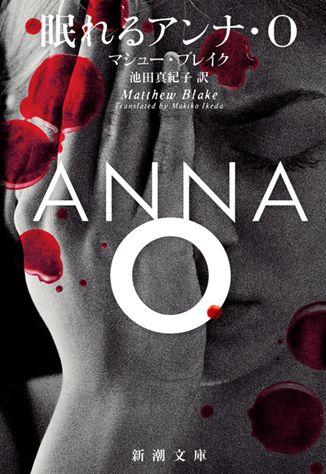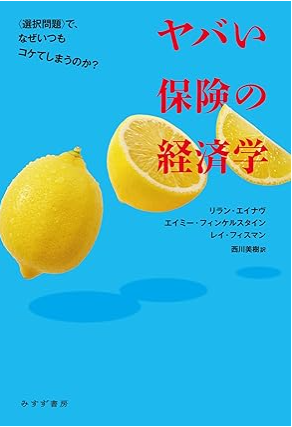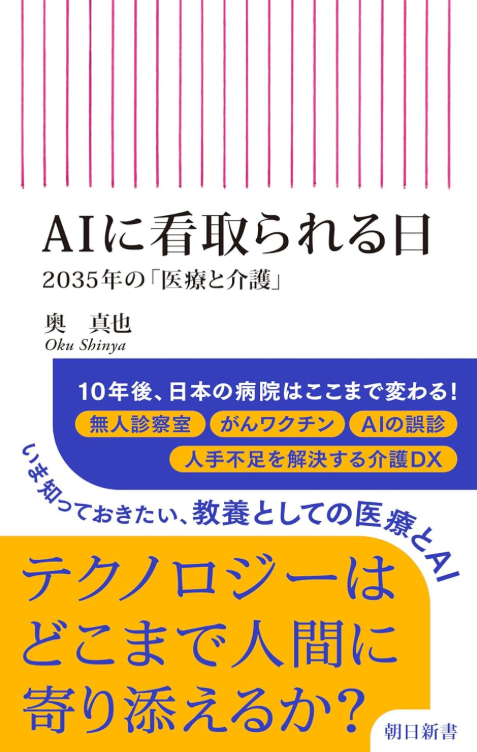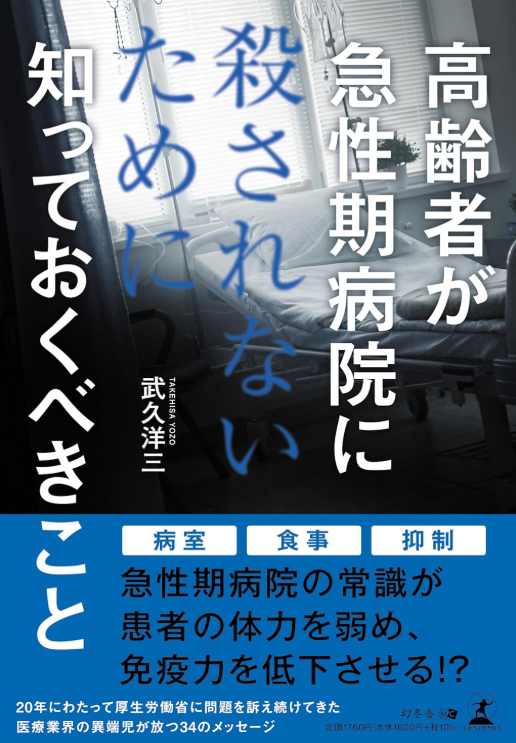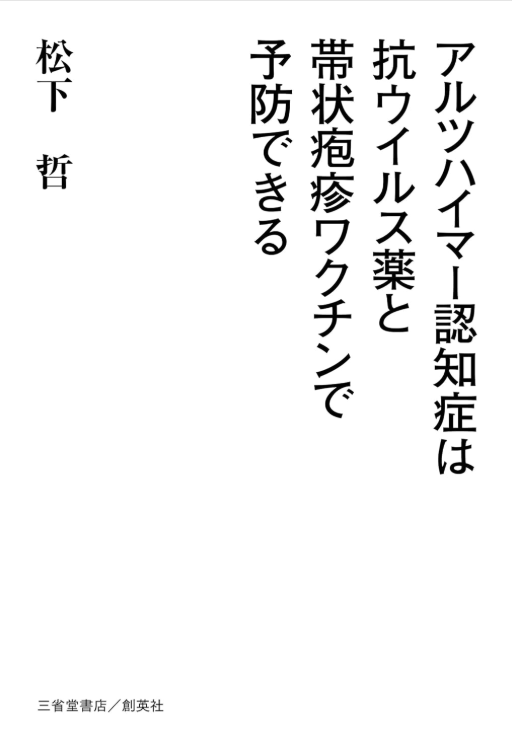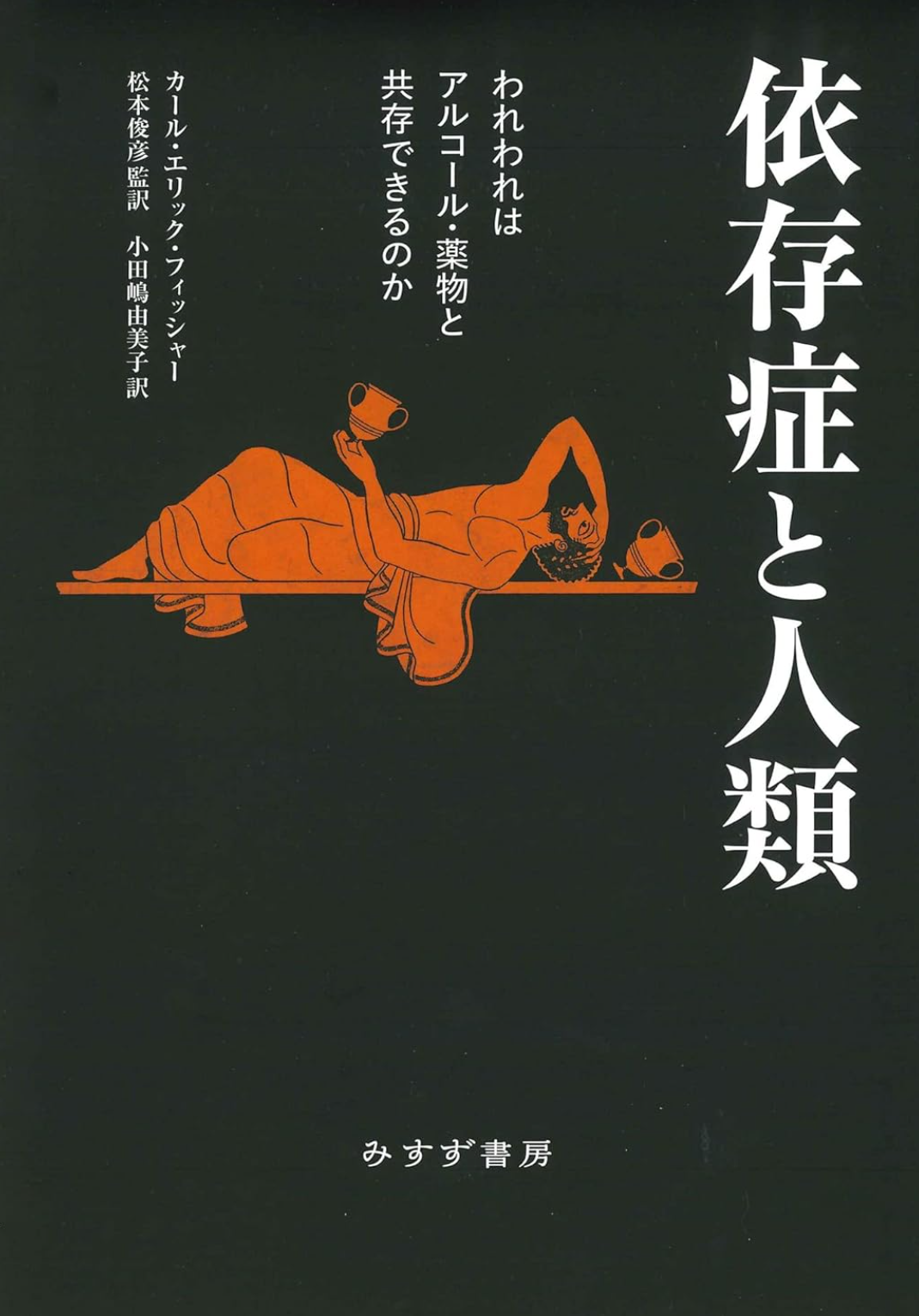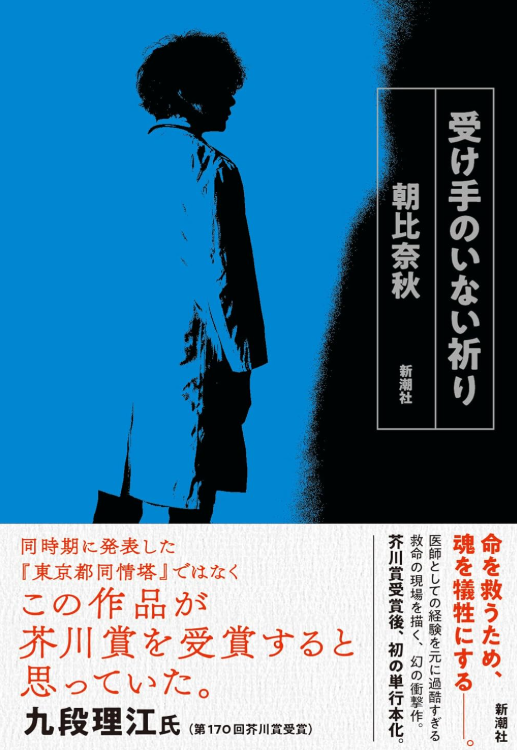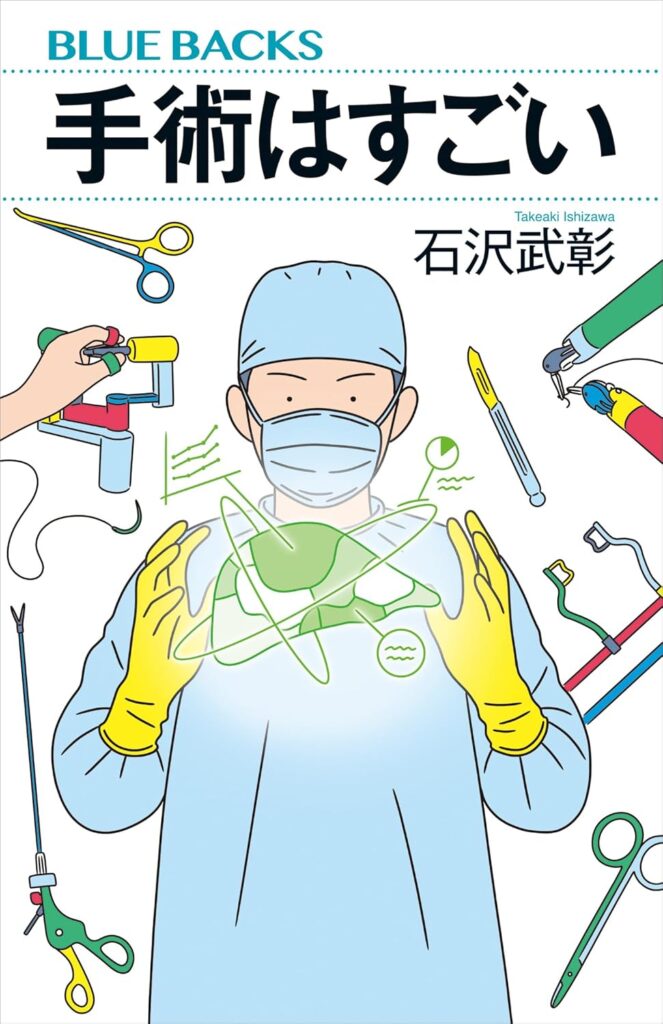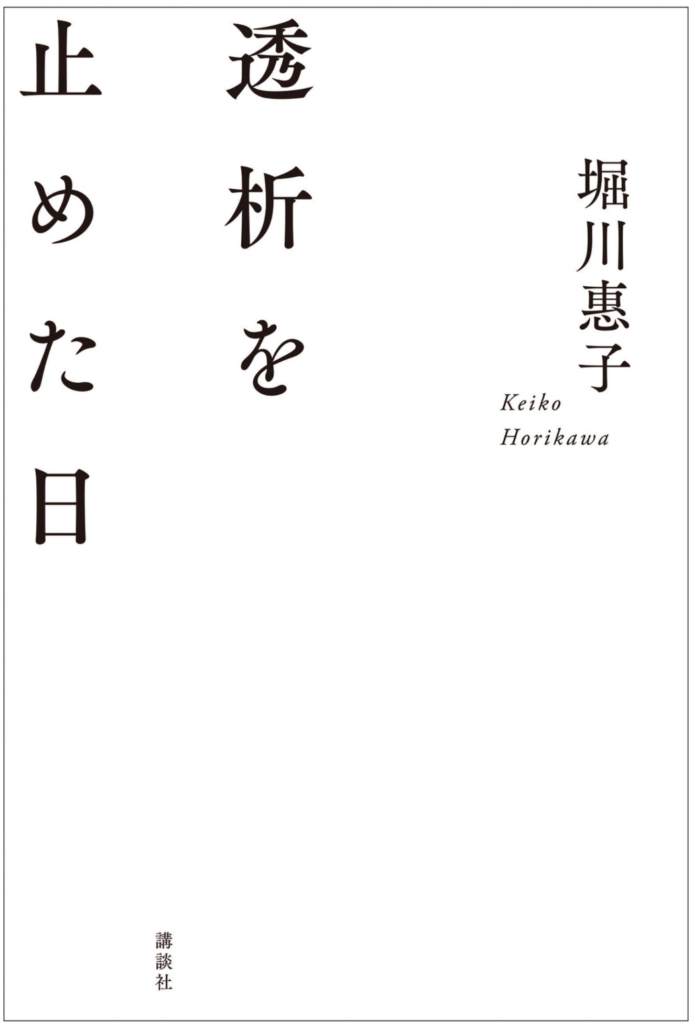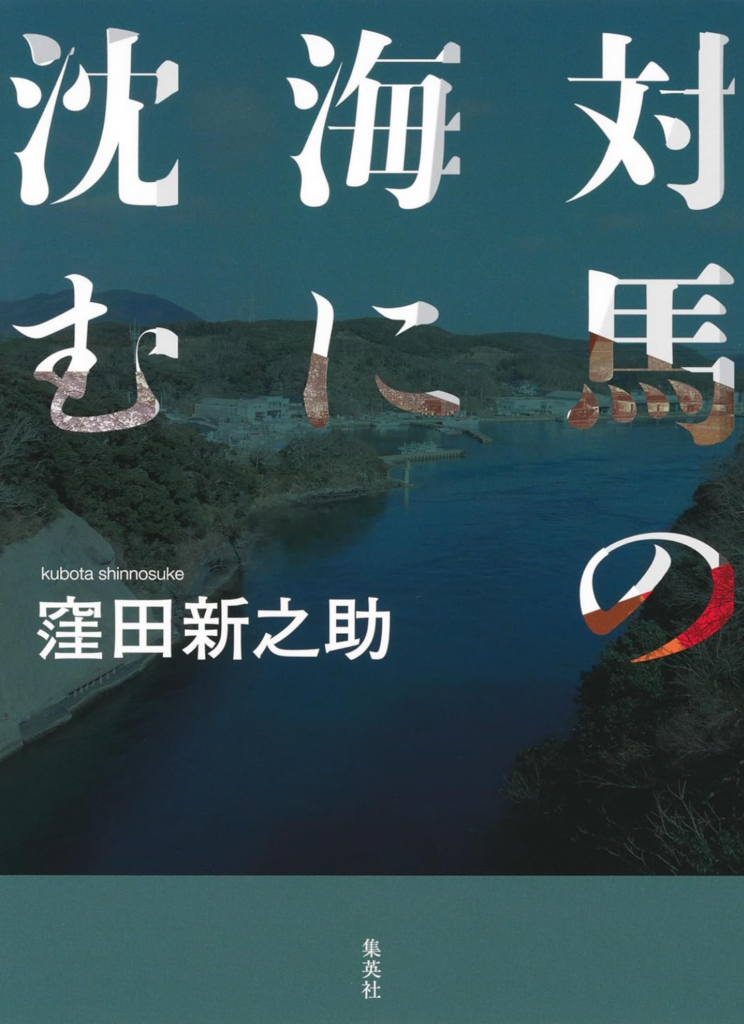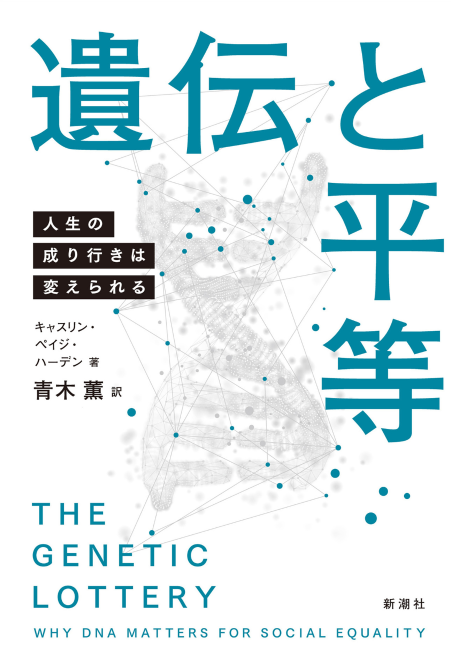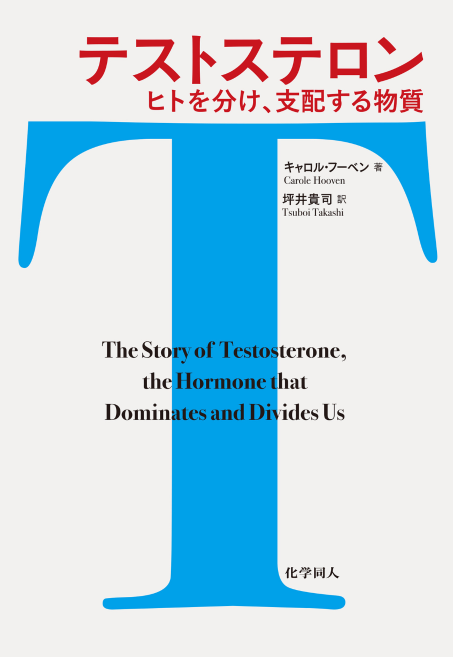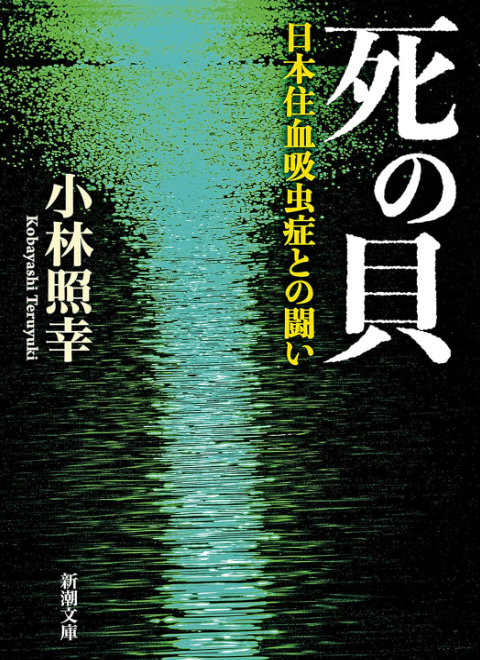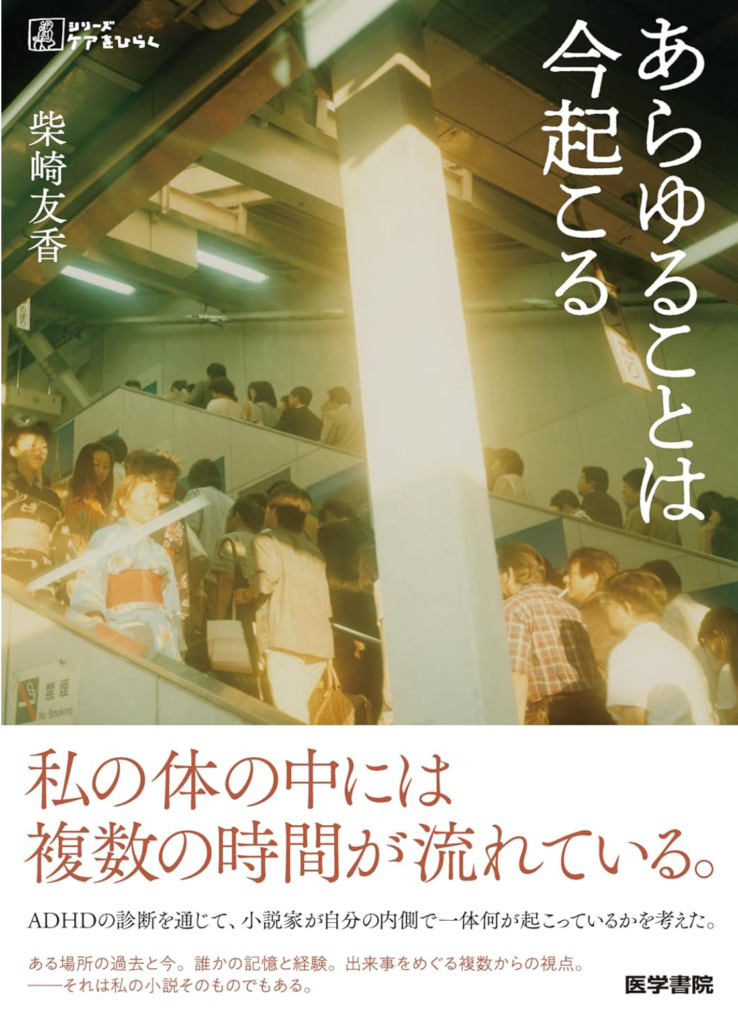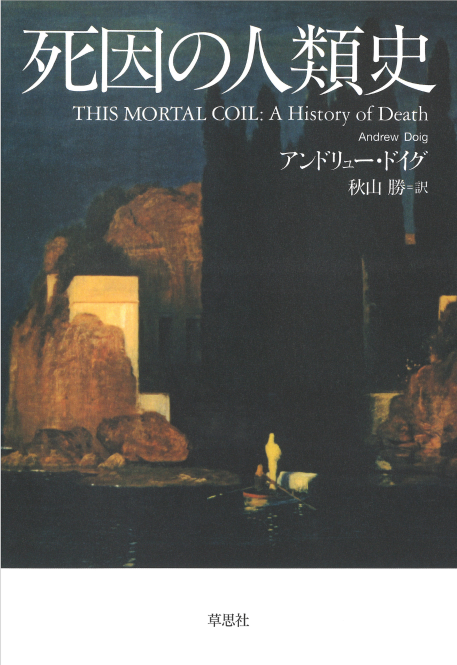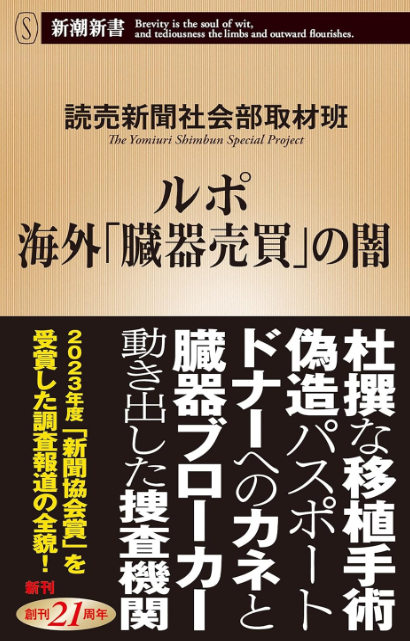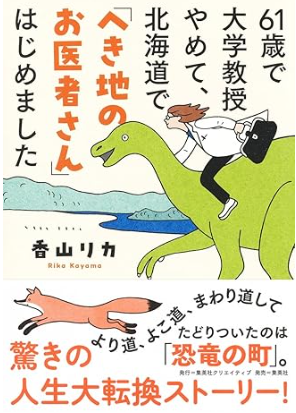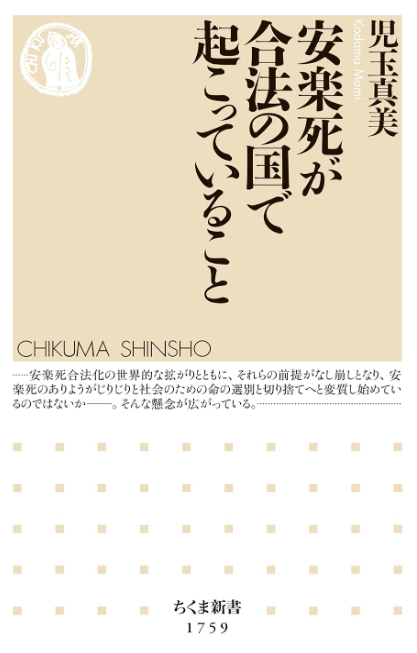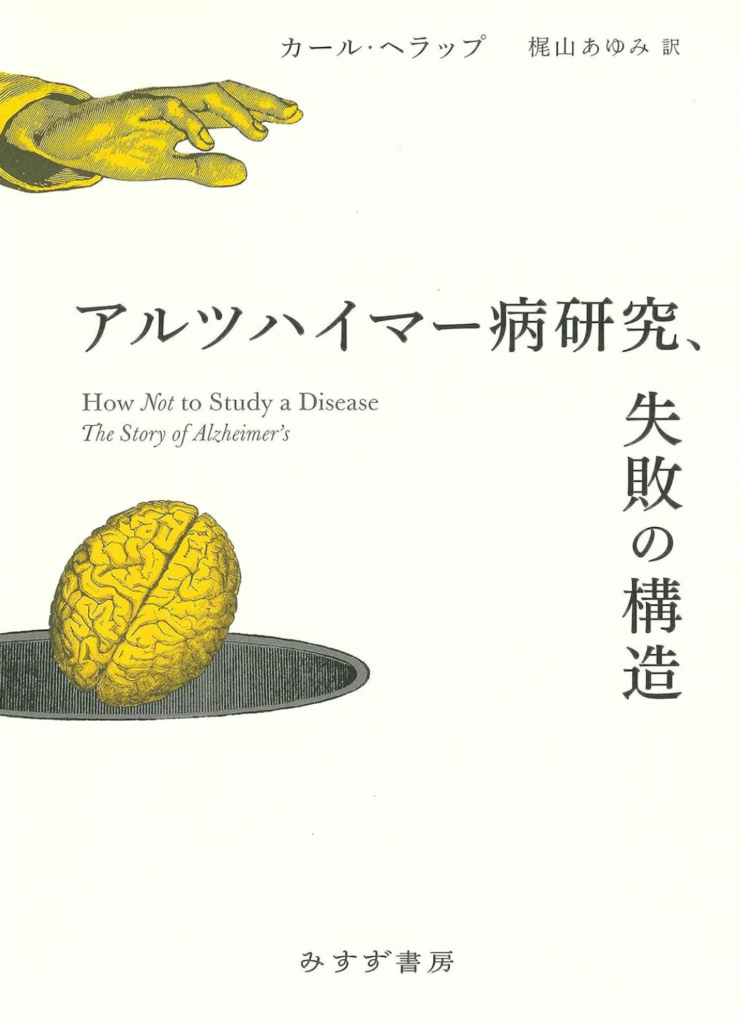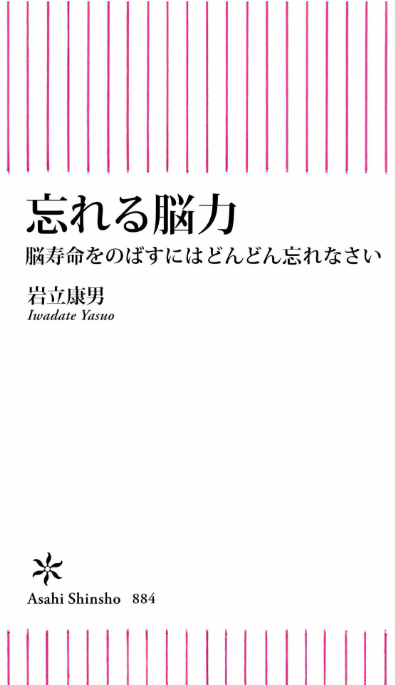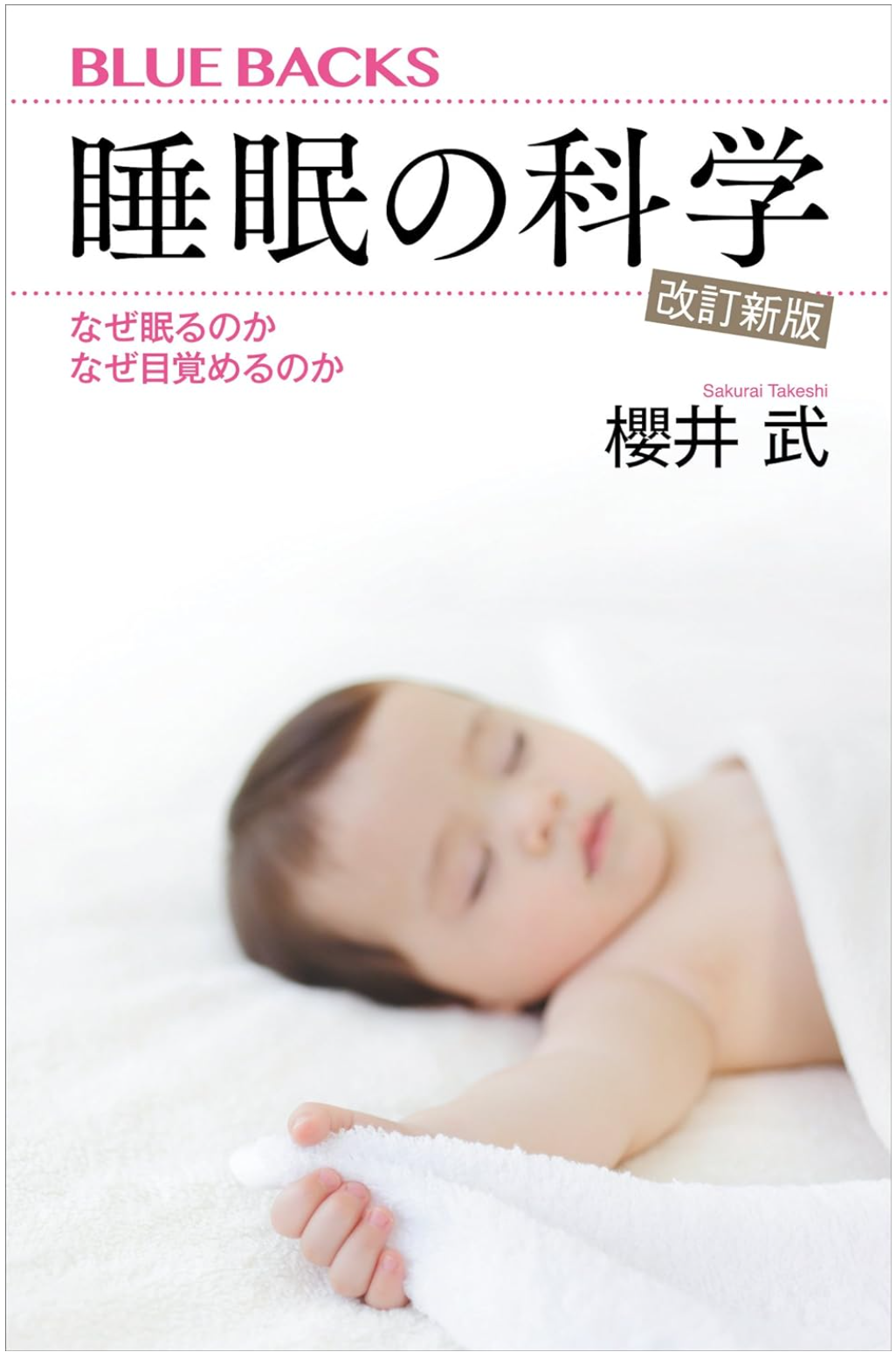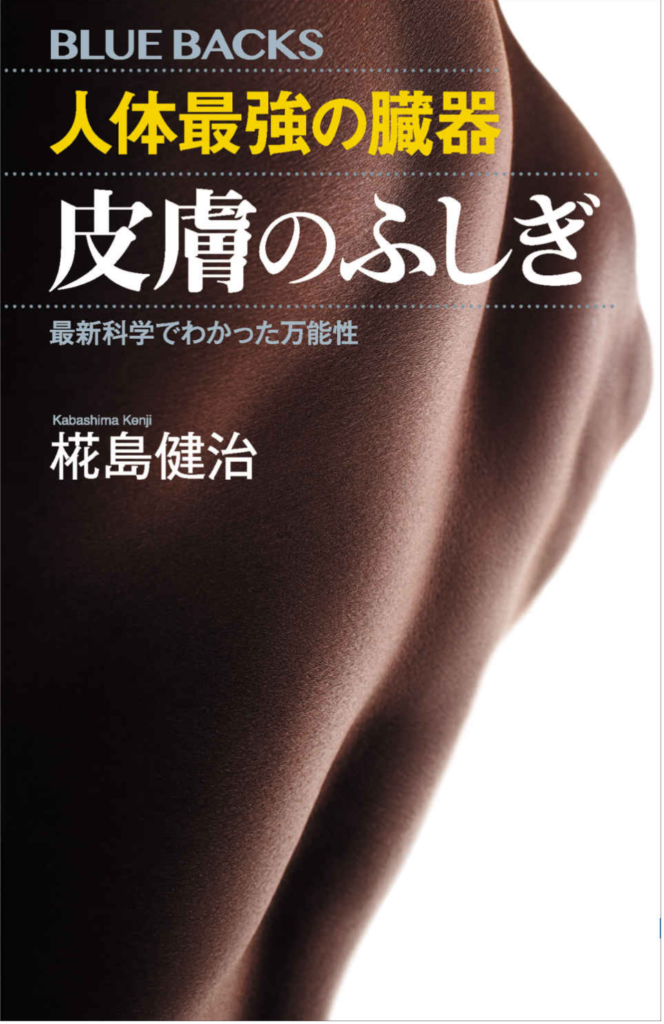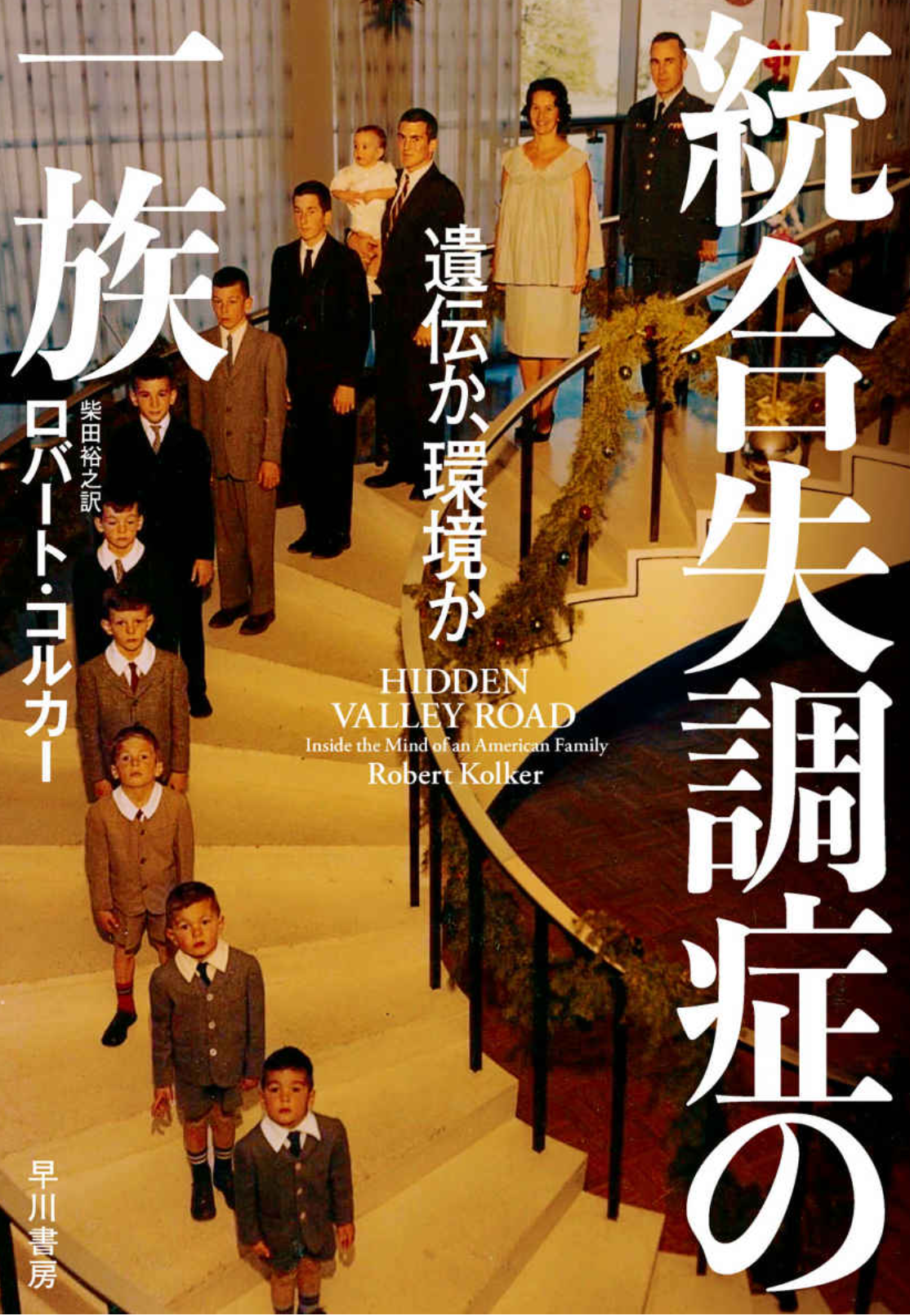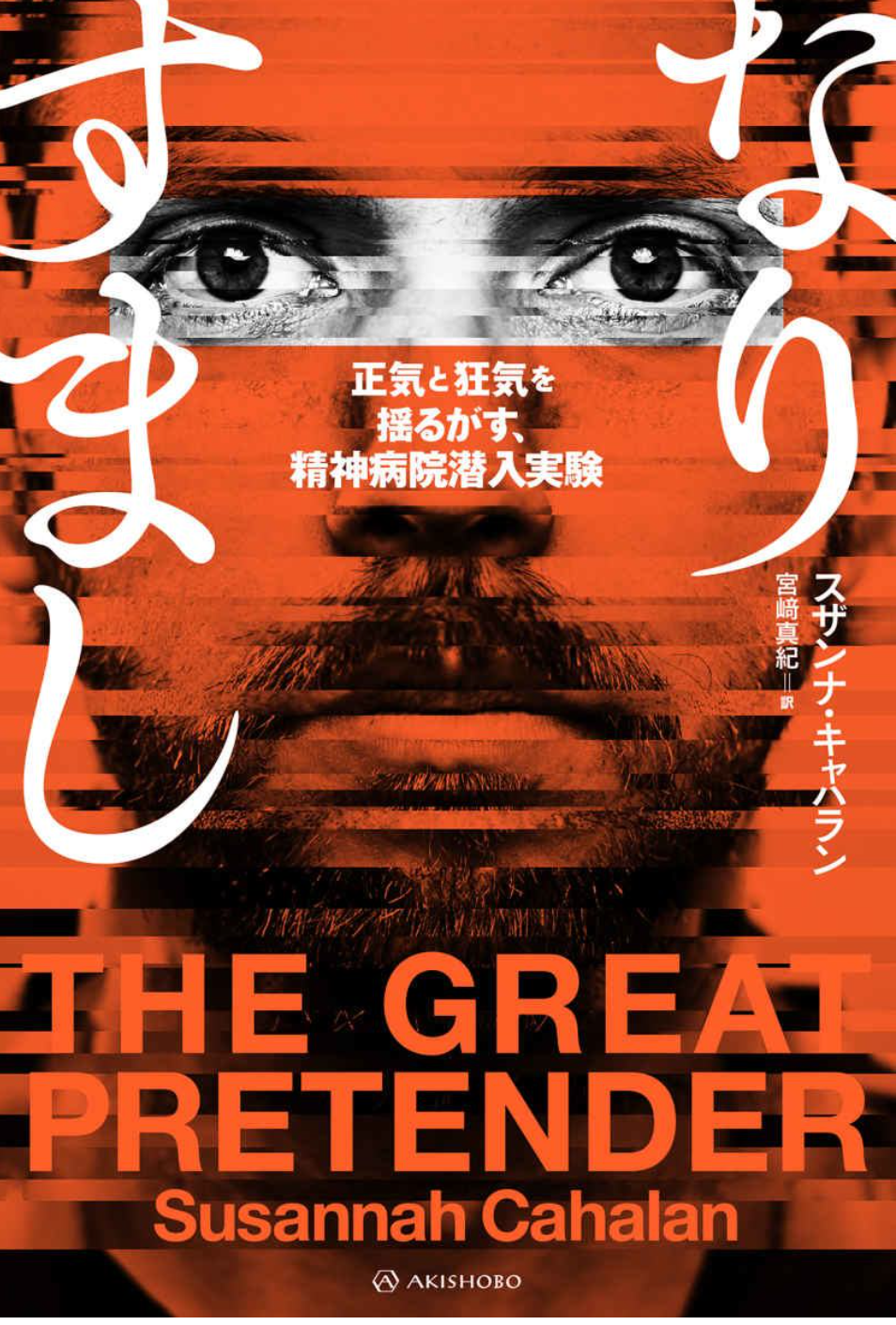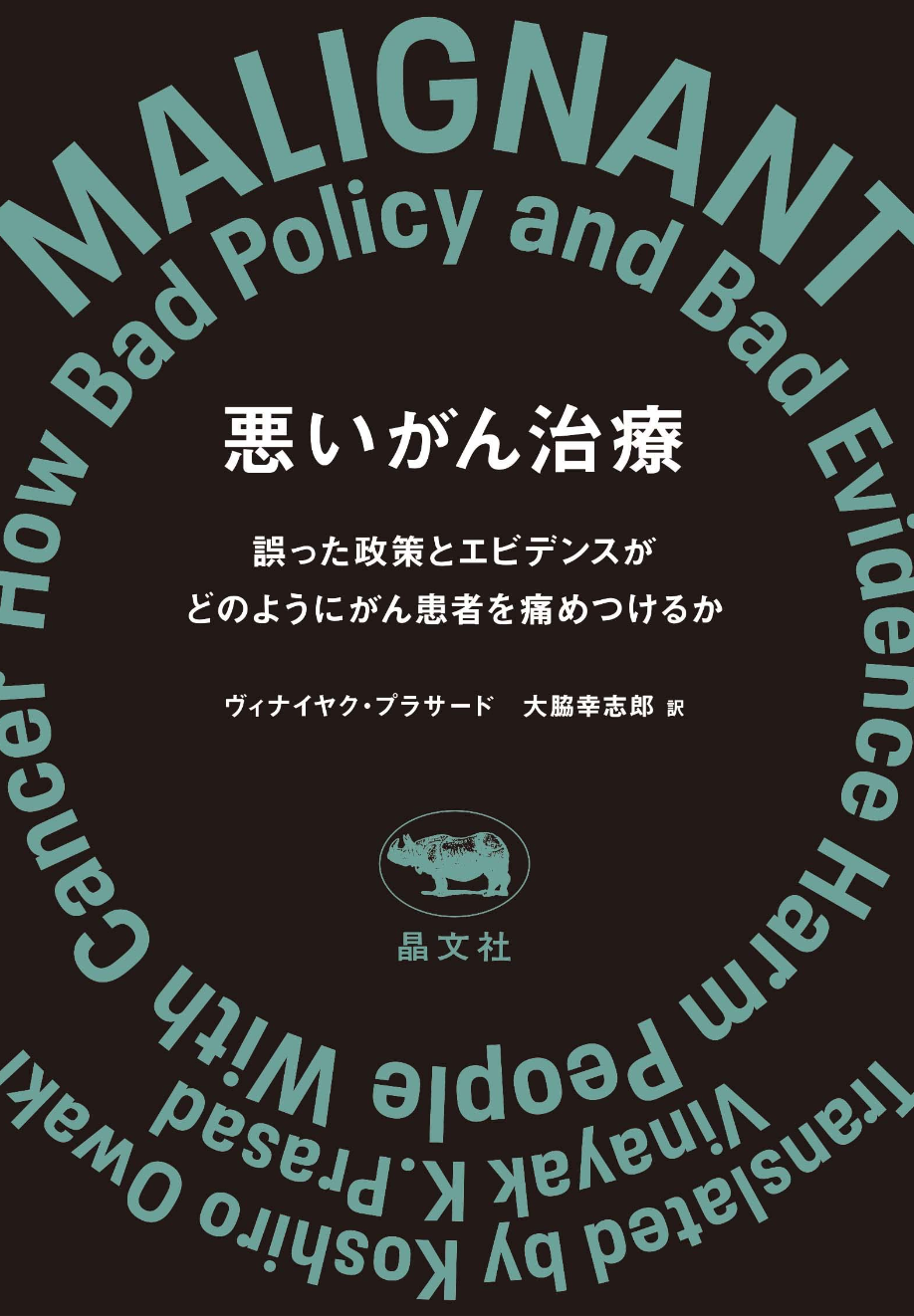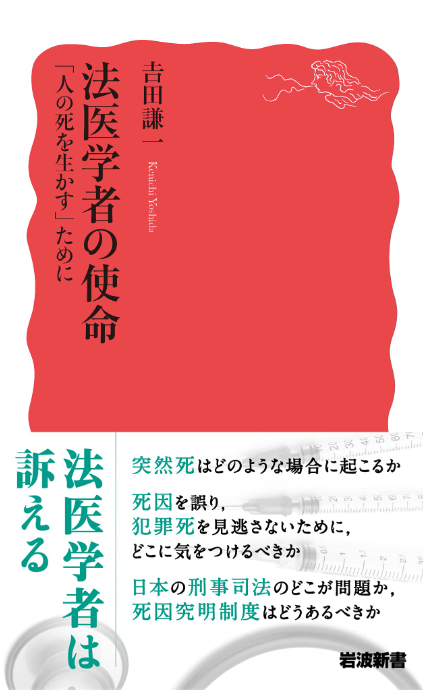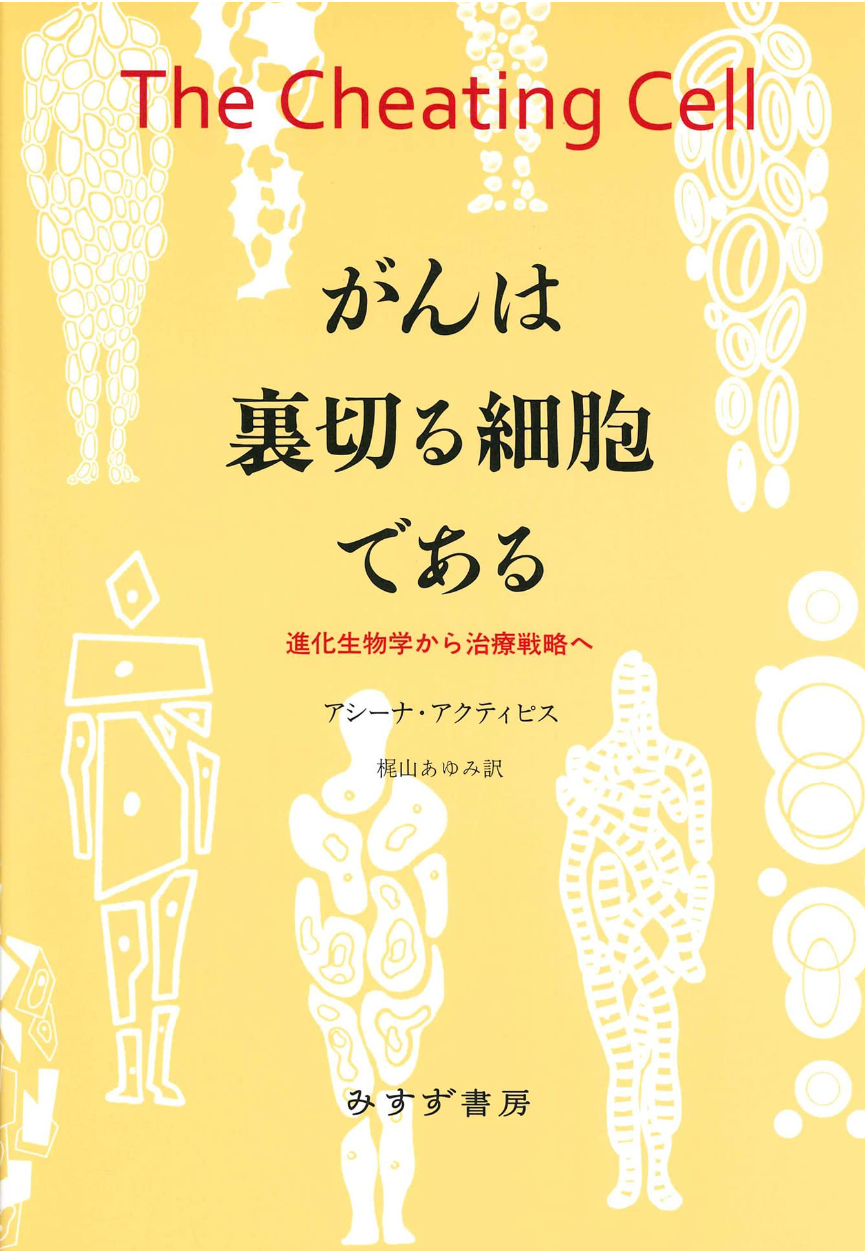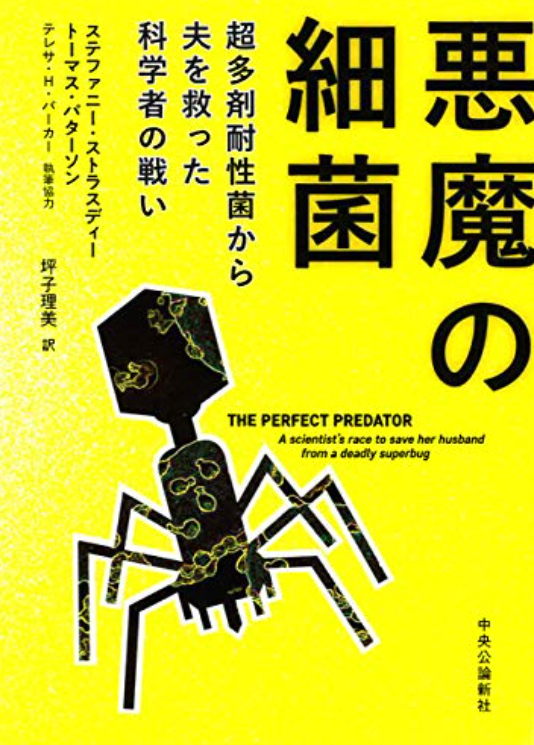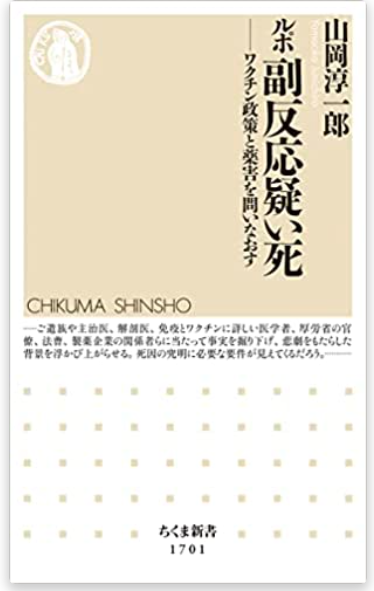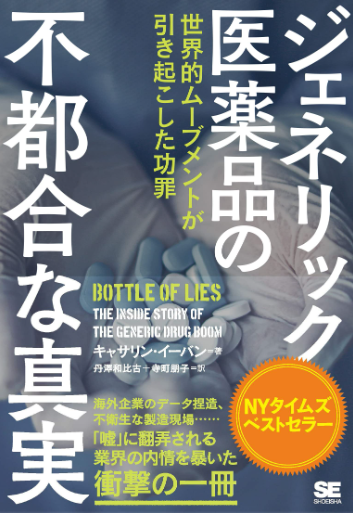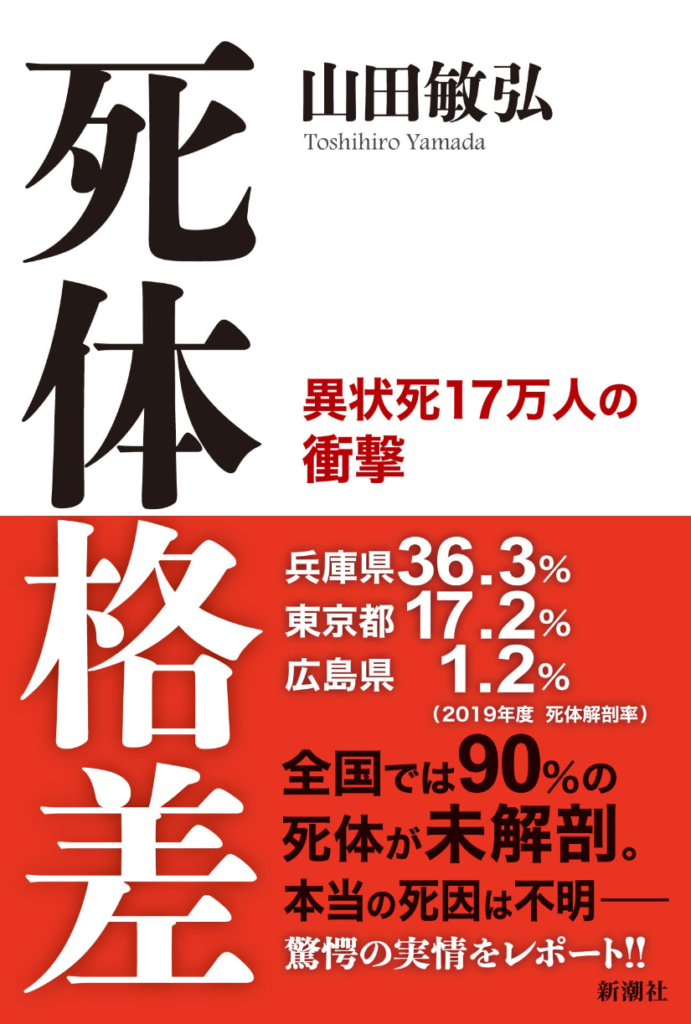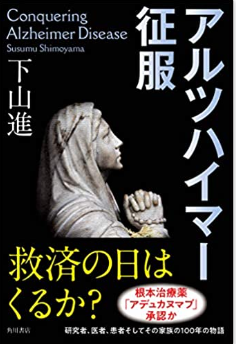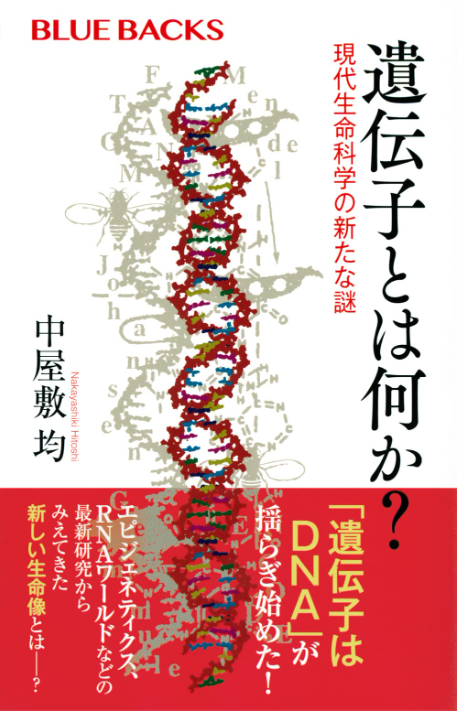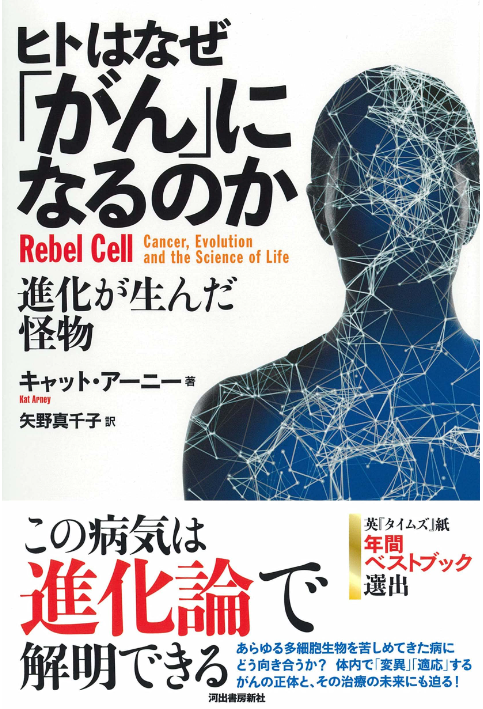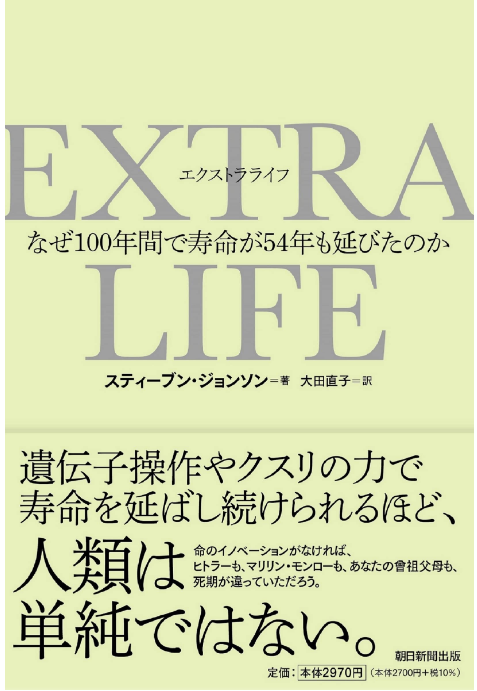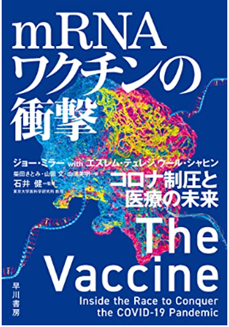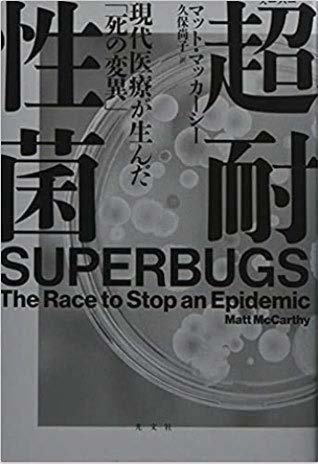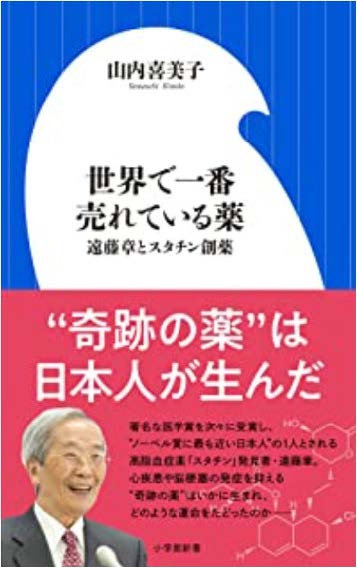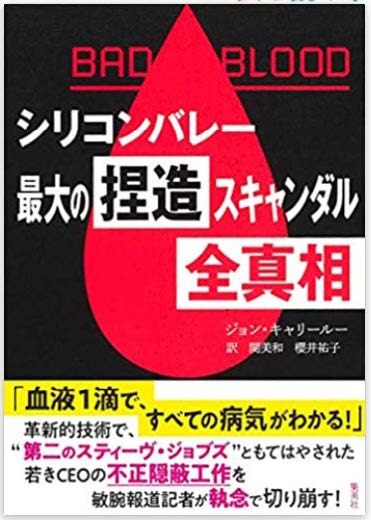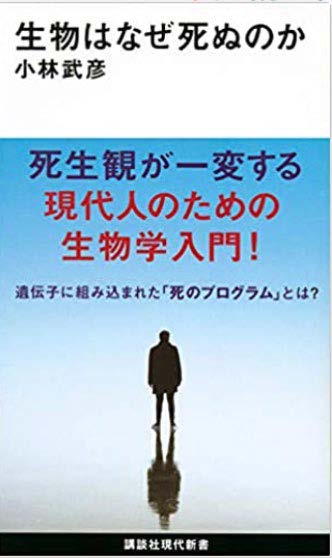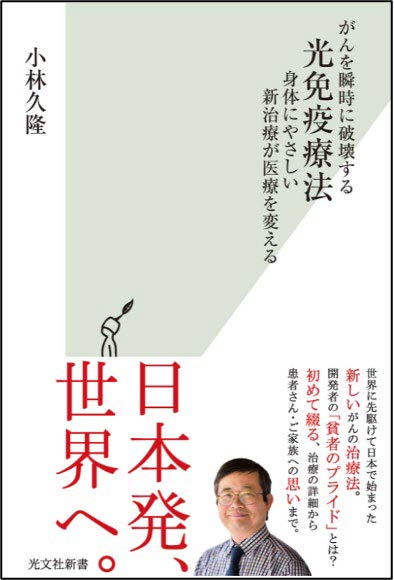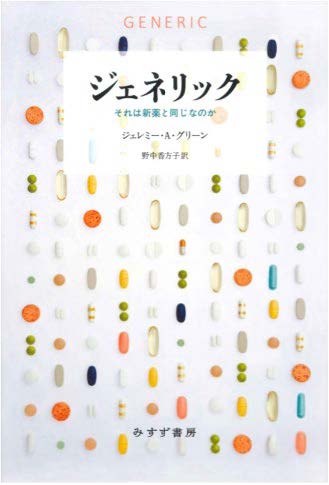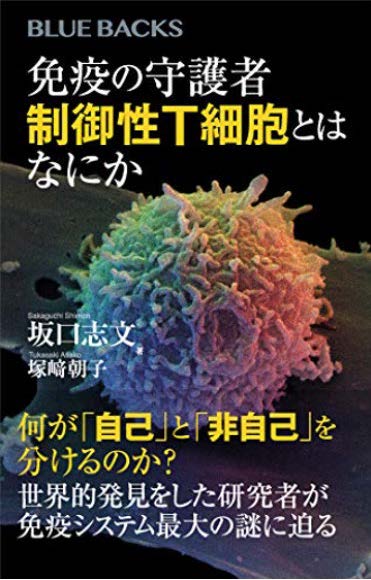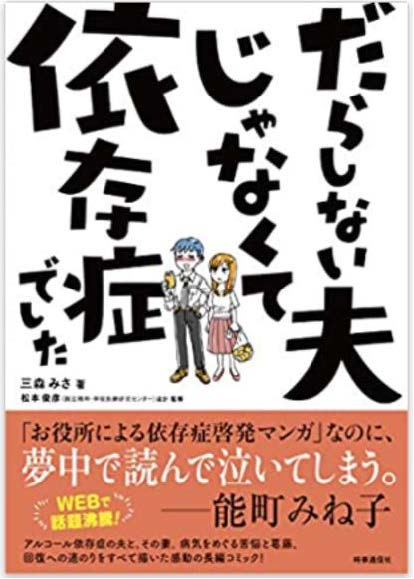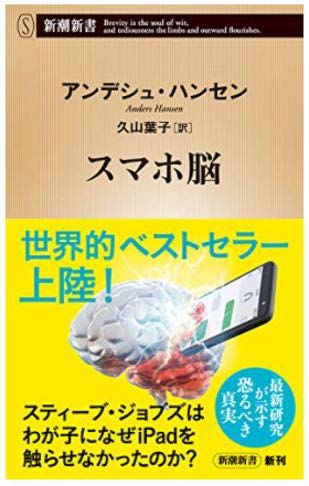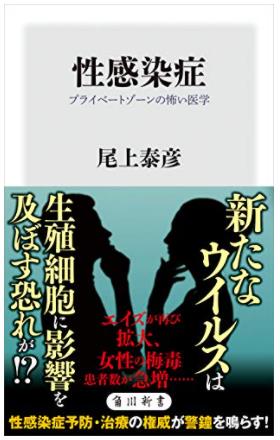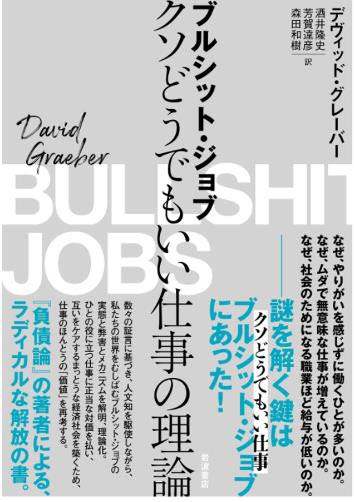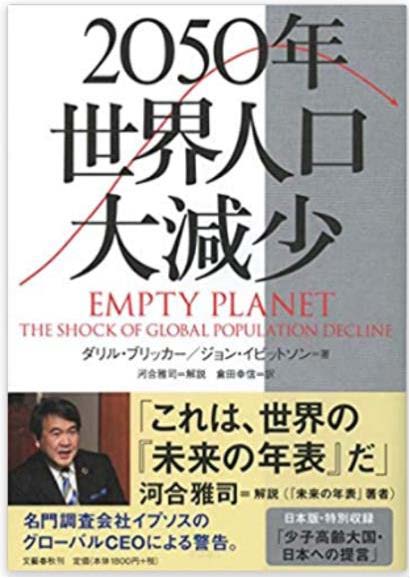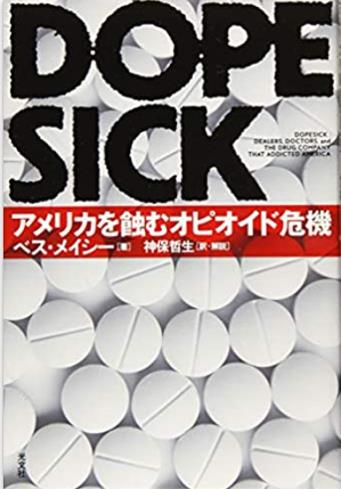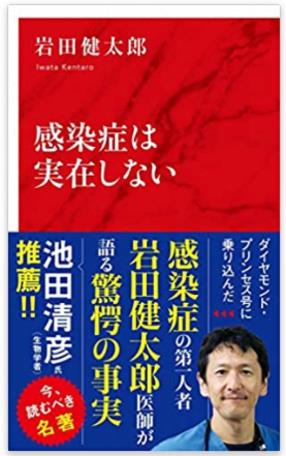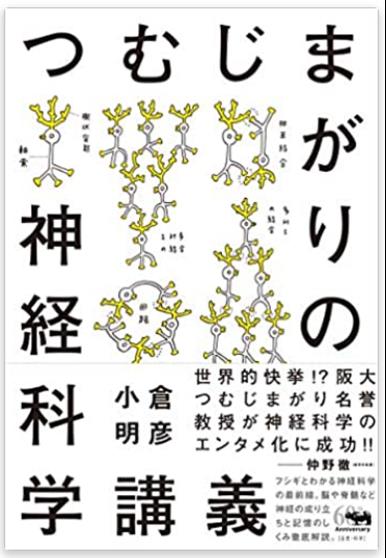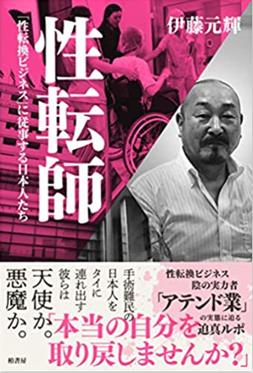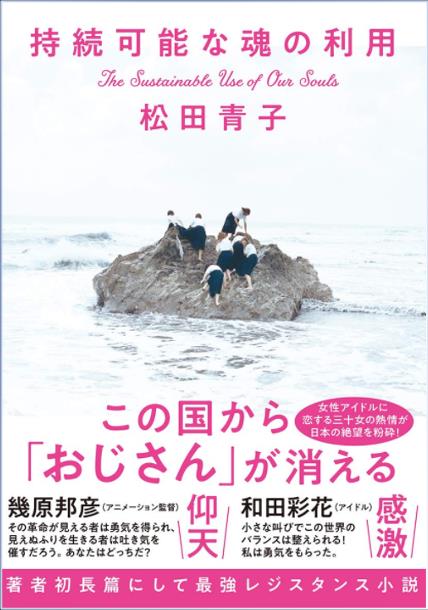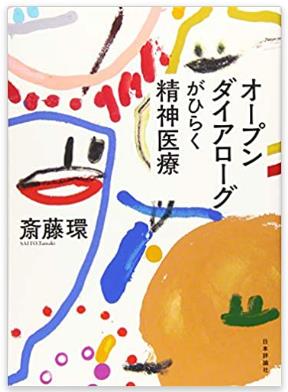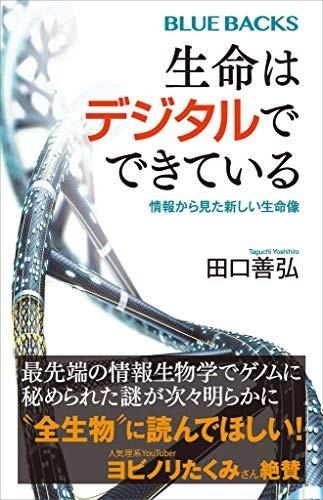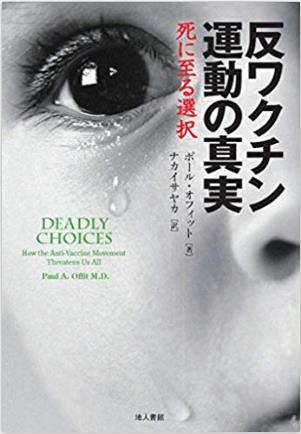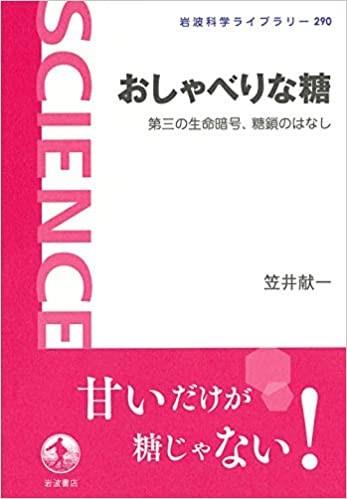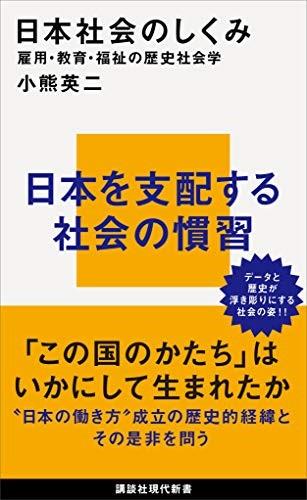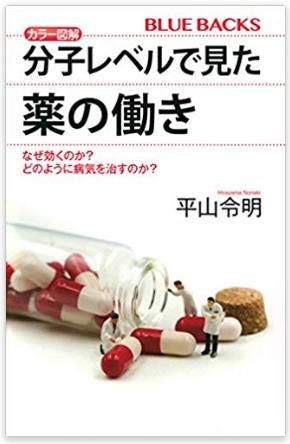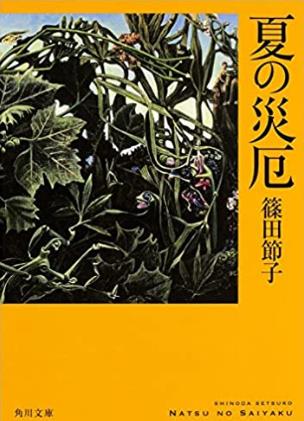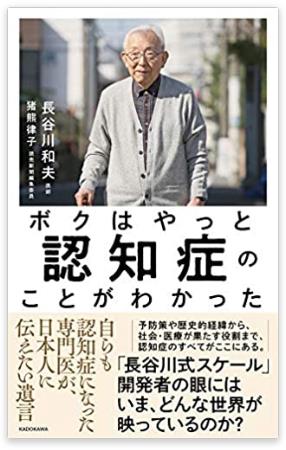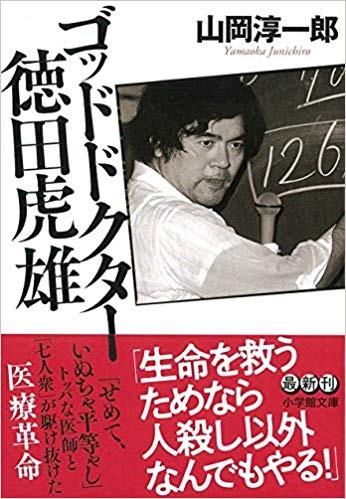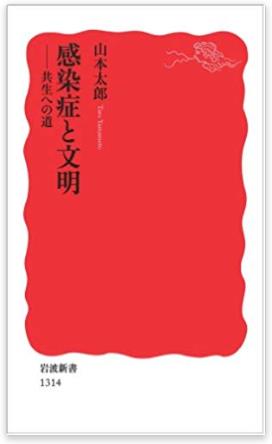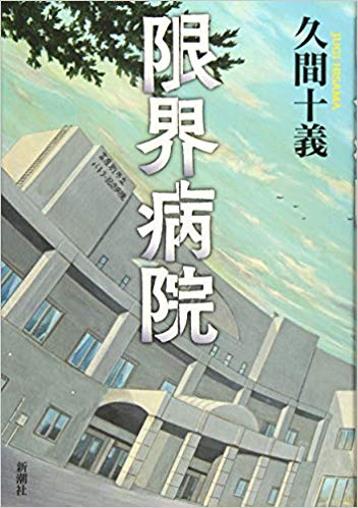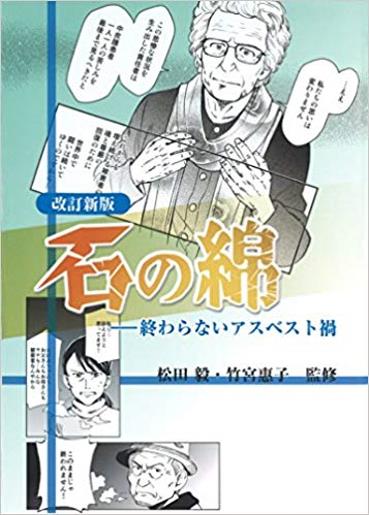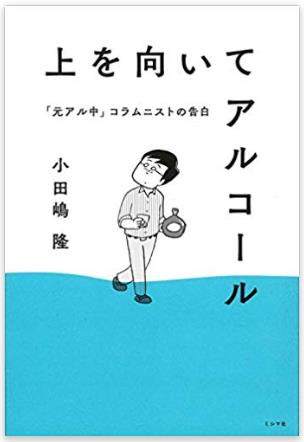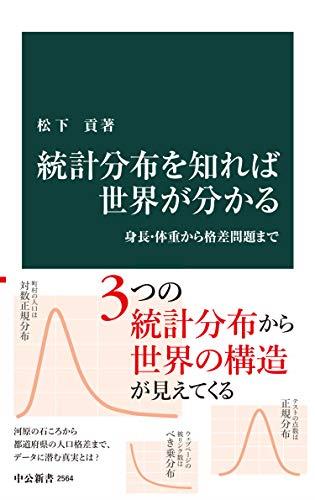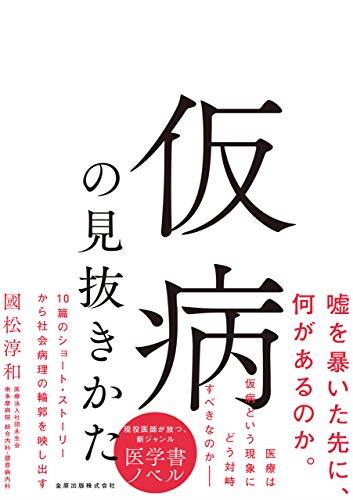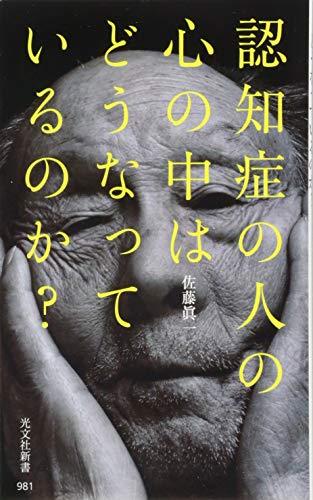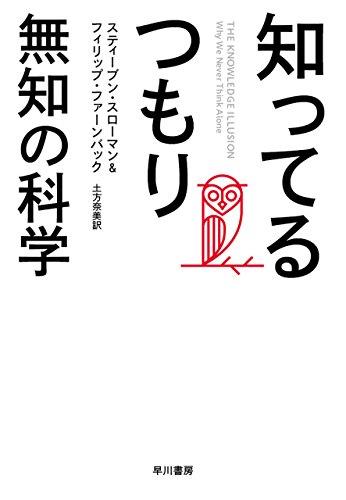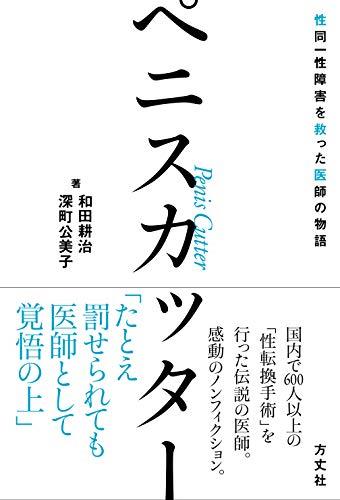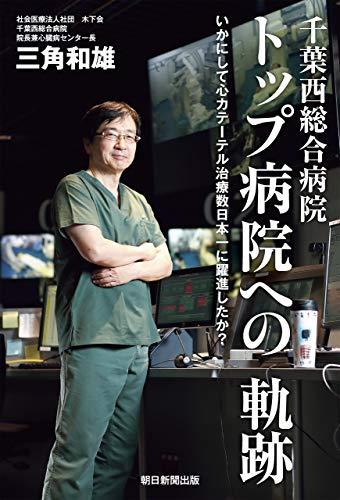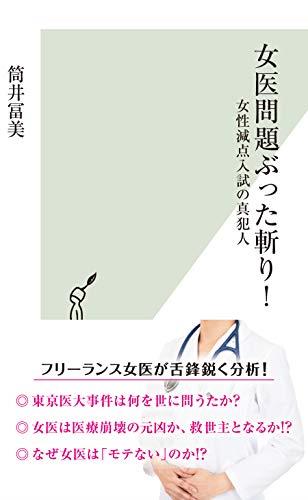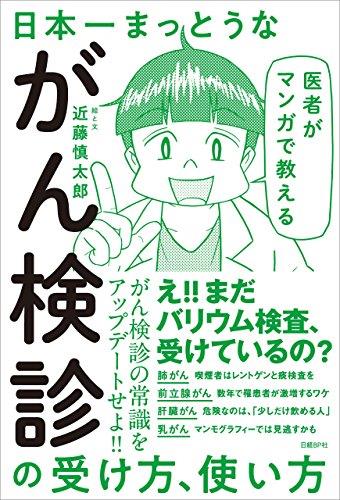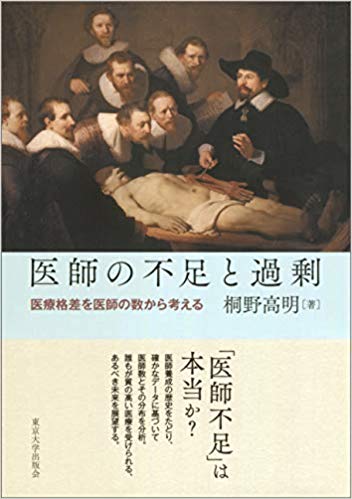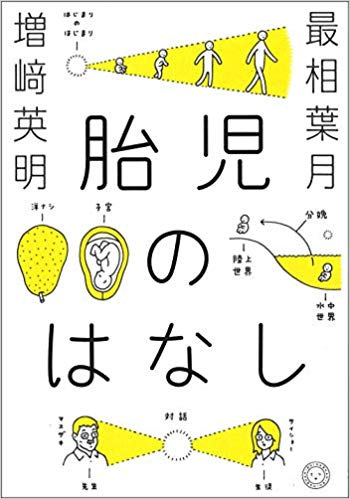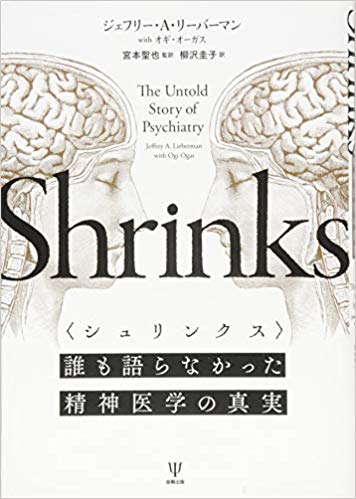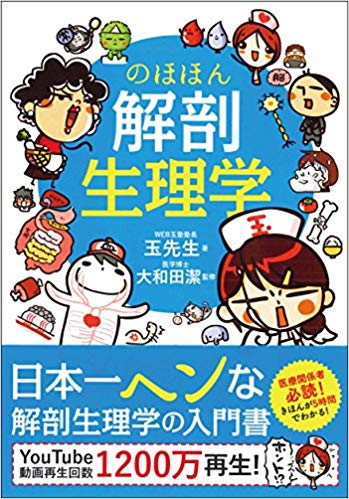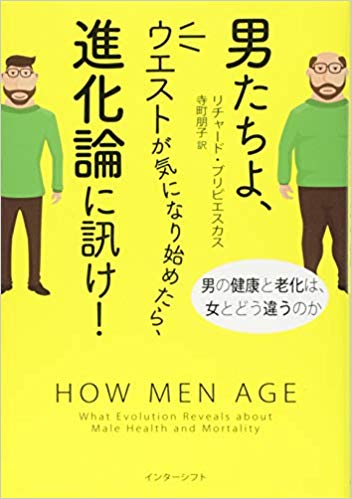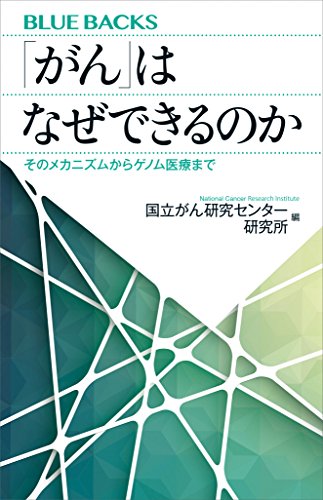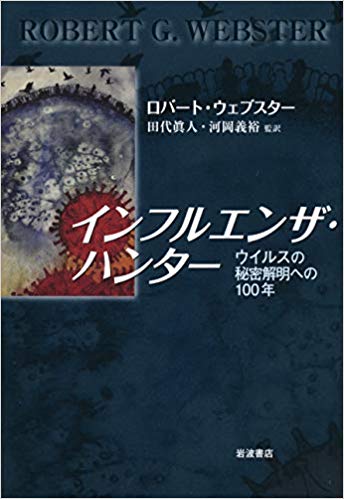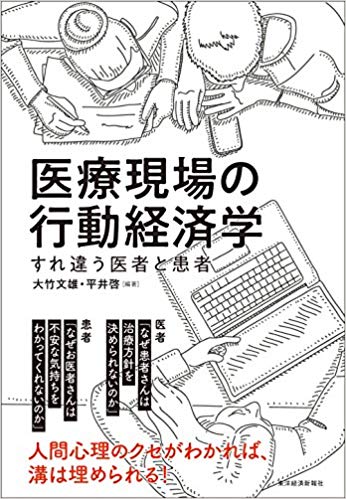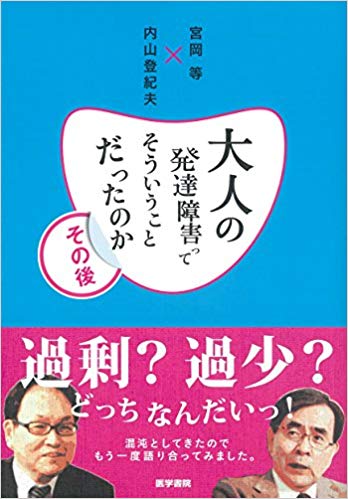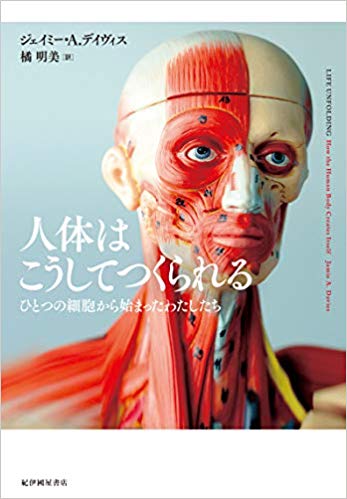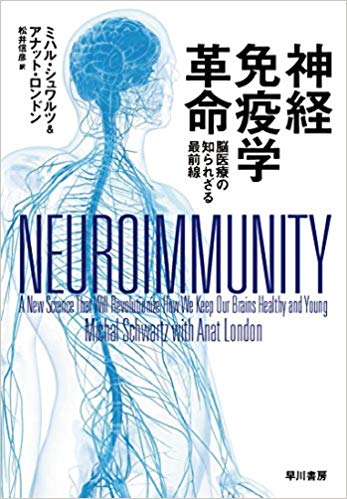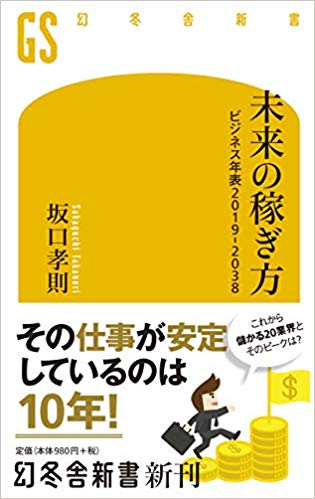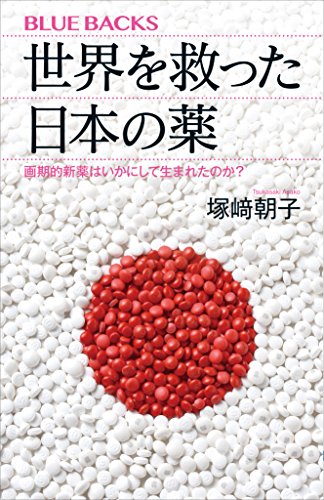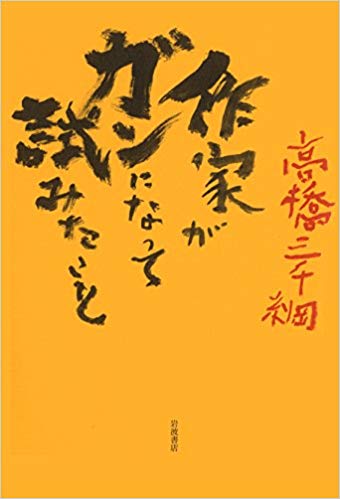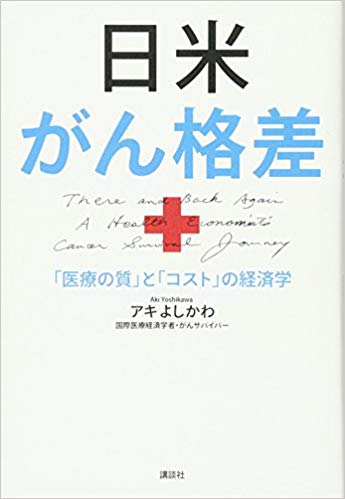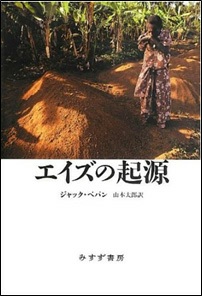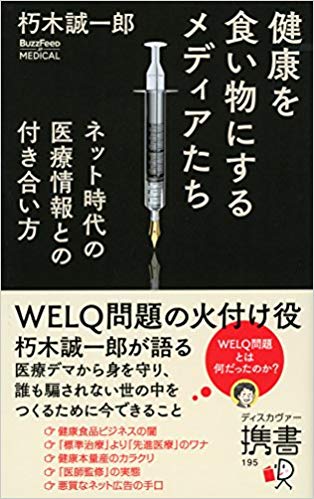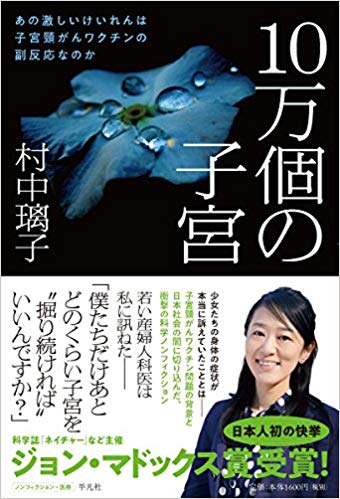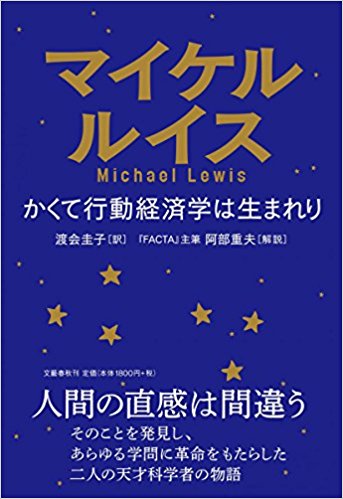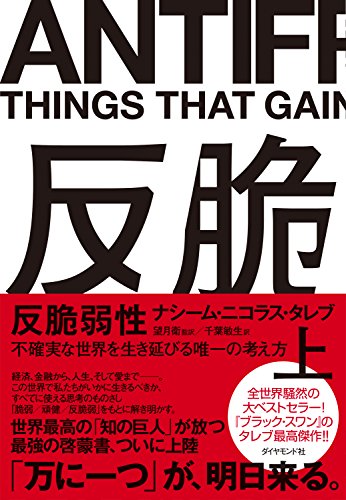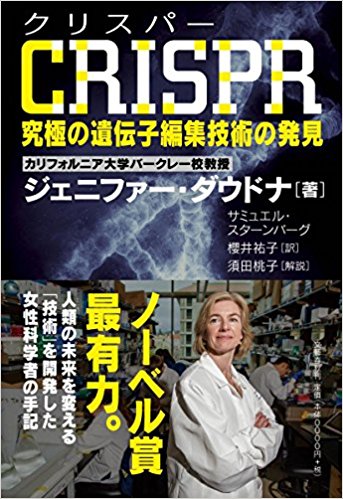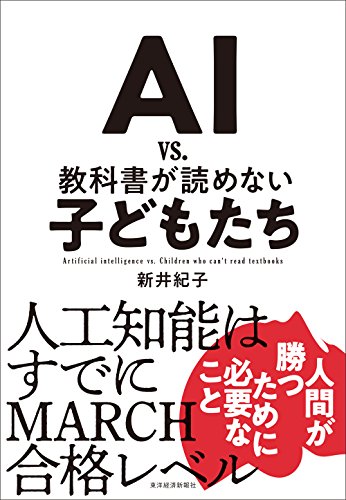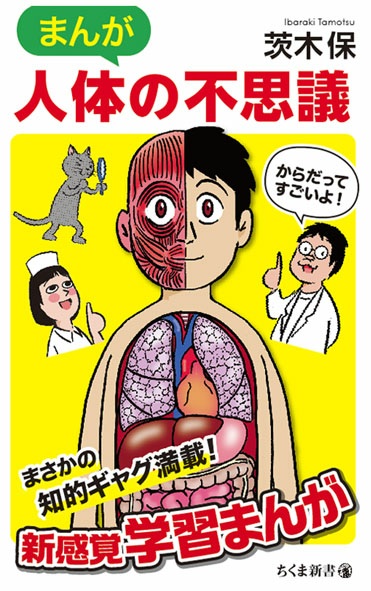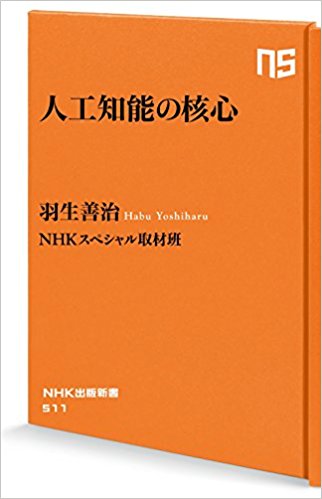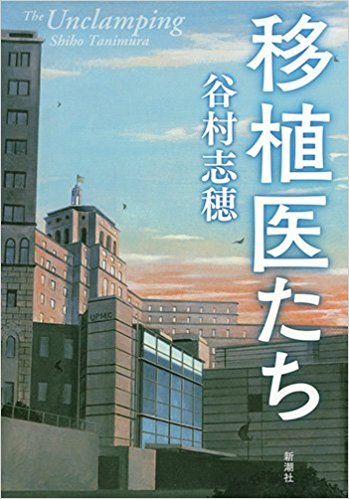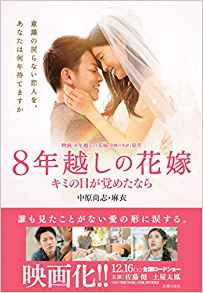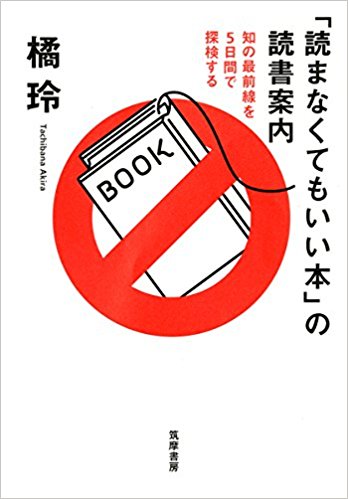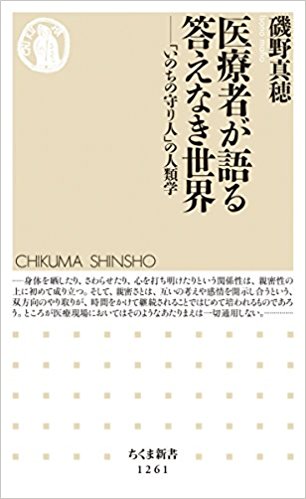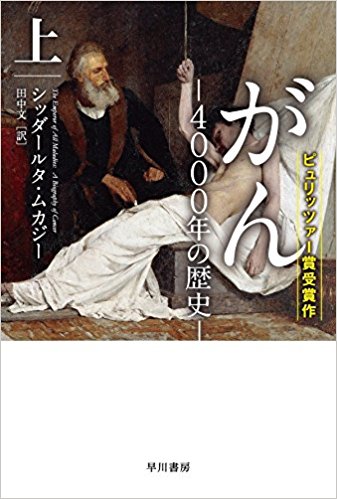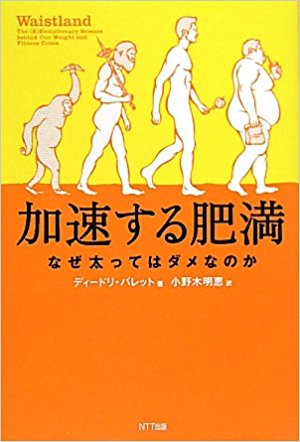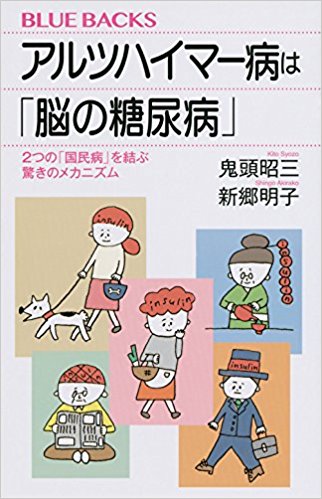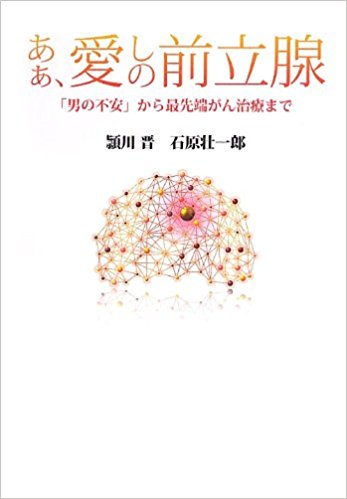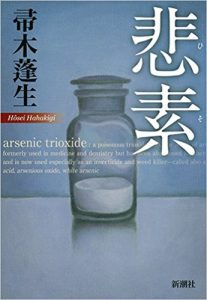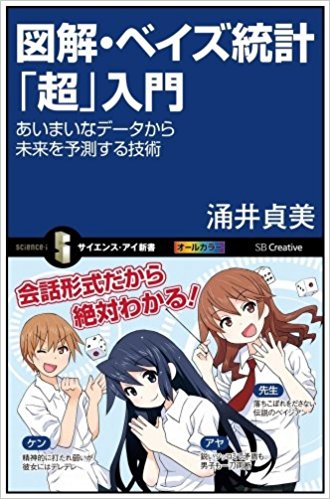査定に役立つブックガイド
元外科医。生命保険のアンダーライティング歴25年。そろそろ前期高齢者。
告知や診断書を見ているとアンダーライティングは常に最新の医療現場と直結していることを実感しますよね。そんな最新医学をキャッチアップしたいと本を読み続けています。そうした読書の中から医師ではなくても「これは面白い!」と思える本をレビューしていきます。レビューだけで納得するもよし、実際に読んでみるもよし。お楽しみください。
読書以外ではジャズ(女性ヴォーカル好き)を聴いたり、大ファンである西武ライオンズの追っかけをやってみたり。ペンネームのホンタナは姓をイタリア語にしたものですが、「本棚」好きでもあるので・・ダジャレで。
ブックガイド(最新号)
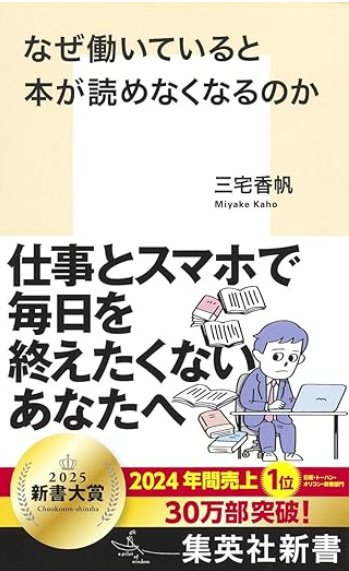
ーー「要約」ですら情報過多なあなたへーー
働いているとなぜ本が読めなくなるのか
三宅 香帆 著
集英社新書 税込定価1100円 2024年4月刊行
「気楽に読めて、査定力もアップする本を!」というコンセプトのこの連載。最近、ふと思うことがあります。このレビューを読んでいる皆さんのうち、実際に紹介した本を手に取っている方はどれくらいいるでしょうか。もしかすると、「レビューだけ読んで、本そのものを読む時間は(あるいは気力は)ない」という方が大半ではないですか。
「本は読めないけれど、スマホでブックレビューやSNSの投稿なら追える」。この奇妙な現象の正体を、文化の歴史からえぐり出したのが本書です。著者の三宅香帆氏は、京都大学大学院を修了後、会社員を経て書評家として独立。昨年のNHK紅白歌合戦では審査員も務めるなど、今や「読書の魅力」を伝える旗振り役として各方面で引っ張りだこの才媛です。そんな彼女が、自身の「会社員時代に本が読めなくなった」という切実な実体験をベースに、現代人の脳に起きている異変を分析しています。
「働きすぎると本が読めなくなる」の正体
本書が指摘するのは、現代社会において労働が私たちの「実存」をあまりに独占しすぎているという歪みです。かつての日本には、学歴や仕事とは無関係に本を読み、知識を蓄えることで自分を磨く「教養」の文化が確かに存在していました。
しかし、2000年代以降の新自由主義的な改革の中で、私たちは「労働によってのみ自己実現を図るべきだ」という思想を強く与えられるようになりました。その結果、労働者の精神的な充足は、読書のような個人的な思索ではなく、仕事の成果によってのみ埋め合わされる構造へと変化してしまったのです。
なぜネットならできるのか?
査定の現場でもそうですが、仕事は常に「全身全霊」のコミットを求めてきます。働きすぎると、脳は極度の疲弊状態に陥り、「仕事に役立つ効率的な情報」や「反射的に楽しめる手軽な刺激」しか受け付けなくなります。
本を読めない理由:本は「ノイズ」の塊です。自分の価値観を揺さぶり、今の仕事とは無関係な思考を強いるため、余白のない脳はこれを異物として拒絶してしまいます。
ネットができる理由:スマホやSNSは、アルゴリズムによって自分が見たい情報だけを流し込みます。それは未知の体験ではなく、脳を「労働」のためのアイドリング状態に保つための、低負荷な燃料にすぎないからです。
私たちは、情報の「摂取」はできても、未知の他者と対話するような「読書」をするための体力を、日々の労働の中で使い果たしているわけです。
査定職人の視点:労働と実存のバランス
私たちアンダーライターや医務職は、日々膨大なカルテや告知書を読み込み、高度な判断を下します。この作業自体が知的で「自己実現的」であればあるほど、プライベートで一冊の物語や論考を読み通すための精神的な筋肉が衰えていく。これは現代的な過労の、最も静かで深刻な兆候と言えるかもしれません。
「入院=給付」という定義が時代の変化とともに揺らいでいるように、「労働=人生のすべて」という定義もまた、私たちの精神的な豊かさを損なうリスク要因として、査定のプロであればこそ再考すべき課題でしょう。
まとめ:読書という「無駄」を取り戻すために
本書は、読書ができなくなった私たちを責める本ではありません。むしろ、そこまで追い詰められている労働環境と社会構造を冷静に分析した一冊です。
このレビューをここまで読めたあなたなら、まだ「リハビリ」のチャンスはあります。仕事に役立つ「情報」を追いかけるのを一度やめて、あえて今の生活には全く役に立たない「無駄で贅沢なノイズ」としての読書を取り戻してみませんか。
さて、読後のおすすめ行動? とりあえず、このスマホを閉じ、鞄の底で眠っている「いつか読もうと思っていた本」を、最初の1ページだけ、仕事のメールをチェックする前に開いてみましょうか。(査定職人 ホンタナ Dr. Fontana 2026年2月)